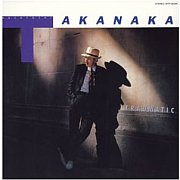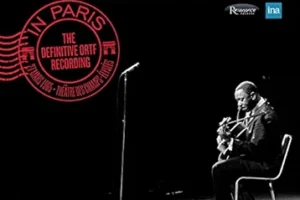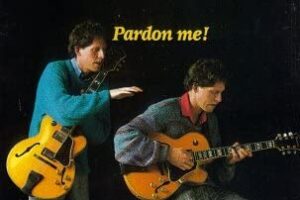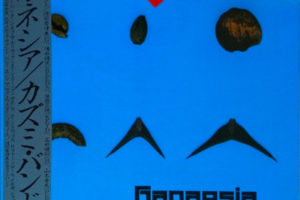(更新日: 2020年7月14日 )
マイク・スターンのサウンドについてまとめてみました。
マイク・スターンのサウンドはトラディショナルなジャズ・ギターとはかなり異なるサウンドで、かなり現代的なサウンドという感じはします。 ネット上で調べると、どうやってあのサウンドを出すかの議論が見つかります。
目次
代名詞的サウンド
クリーン・歪み系でもディレイ・コーラス系が基本のサウンドだと思います。
残響系
残響系はかなりこだわりが強い感じはします。かけっぱなしのディレイ(Telecaster Discussion Page Reissueによれば、delay = 221 ms , 4 repeatsがキモだとか)と飛び道具的なロングディレイの2つのディレイを使っていますね。
モジュレーション系
モジュレーション系は、ソロでメジャーデビューした時期から長い間はピッチシフターで微妙にずらした音を混ぜるディチューンが代名詞でした。 最近はコーラス(CH-1)も使っているようです。(参考: Mike Stern(マイク・スターン)氏ライブレポート!、Mike Stern Gear 使用機材 @Blue Note TOKYO 20150608 )
レコーディングは基本的にステレオアウトしています。モジュレーション系の出力をステレオにしているのではないでしょうかね。聴こえ方がステレオ・コーラスっぽいので。 2009年のインタビューではSPXでステレオ・アウトしていると言っています。
歪み系
歪みは長らくDS-1が代名詞的でしたが、最近はSD-1やBD-2Wがボードに乗っています。

再現例
YouTubeで見つけた、サウンドの再現例です。かなりそれっぽいです。ここでは TC ELECTRONIC / Flashback と BOSS Super Shifter
(リンクは後継機のPS6)を使っています。

ピッチシフターはディレイを短めにするほうがダブリング効果を抑えられます。ディレイが長めの場合、ぼくとしては、ダブリング効果が少し欝陶しい時があります。
あと個人的にはディチューン・エフェクトは揺れないコーラスな感じですが、コーラスでも良いかもって思う時もあります。

マイルス・バンド時代
We Want Milesなどではたぶんラージヘッドのストラトを使っています。 全体にリア・シングルらしいサウンドですが、トレブリーではなく絶妙にセッティングされています。 これは真似したい。
残響系はディレイがかかりっぱなしです。要所要所でロングディレイの飛び道具を使っています。 残響系については、この頃にすでに使い方がほぼ固まっているのが分かります。
歪みはオーバードライヴっぽい。DS-1なのかは分からないですね。 モジュレーション系はかかっていないように聴こえます。
ソロ・メジャー・デビュー後
ギターはテレキャスターにネック側ピックアップがダンカン ハンバッカー 59、ブリッジにビルローレンスL-250だったような…。
これは”Upside Downside”のジャケットに写っているギターでしょうね。ダニー・ガットンから買ったと言っています。
“Downside Upside”では、ピッチシフターやオクターバーを駆使したサウンドになっています。 “Little Shoes”ではテーマ・ソロにオクターブ上を混ぜて弾いています。この頃はSPXを2台つかっていた時期だと思います。 ディチューン系と1オクターブ上の音用なのかもしれません。
1986年頃のボードにはたしかBOSSのオクターバーが乗っていました。 この曲はディレイの使い方も分かりやすいです。ディレイ・タイムが短めでかなりアナログディレイっぽいサウンドです。 ジャコ・パストリアスも参加していた”Mood Swing”では歪みにオクターブ下の音を混ぜて弾きまくり。
SPXやヤマハのFシリーズアンプが見えるインタビューです。
この頃はすでにヤマハのPacificaになっています。ブリッジ側のピックアップはダンカンのHot-Railsになっていると思います。
“Time In Place”以降もほぼ同じようなサウンドですね。
最近
基本的にサウンドの傾向はかわらず、使うエフェクターが少し変わっているだけでしょうね。
おわりに
一流のプレーヤーは、たいてい一聴して分かる代名詞とも言えるサウンドを持っているものです。 そして一流のプレーヤーのサウンドはフレーズに負けず劣らず魅力的なことが多いと思います。 このマイク・スターンしかり、パットメセニーしかり、アラン・ホールズワースしかり。
自分のサウンドを確立するのは、結構難しさを感じています。ぼくなんかは、どんどん好みが変わってしまうので、なかなか自分らしいサウンドが定まりません。 エフェクターだけでなく、ギターやピックアップ、そしてなによりタッチの研究が必要です。
マイク・スターンのサウンドを真似するのも良いですが、自分のサウンドを追求する方が大事なんでしょうね。