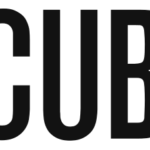哲学的な本だな、と思いながら読んでいましたが、どうやらハイゼンベルクもそれが狙いらしく、プラトンを意識して書いたようです。 プラトンを意識する時点でもうちょっと違う。「哲学」の伝統を感じます。 Ph.DのPhはフィロソフィーが語源ですから、本当のところは科学だって哲学に包含されているわけです。 そんなの普段は忘れていますが、この本ではそれを思い出させてくれます。
全体的に物理そのものの話はなく、思考や思索の足跡をたどるといった風情が相応しい。 プラトンなんて読んだことはないですが、対話の形式の著作があることは知っています。 どうやらヨーロッパにはそういう伝統が文化としてあるようで、この本も対話がとても多い。
伝統という意味だと、哲学的な議論をすることに価値を置いているのが分かって、そこにヨーロッパの雰囲気を感じることがでる。 一部、プラグマティズム的な科学への態度を批判的なくだりもあり、ヨーロッパの科学者がアメリカの科学者との気質の違いに敏感だったのが分かります。 この時代までなのかも知れませんが…。
対話のなかでは、やはりというか、ニールス・ボーアとの対話の分量は多め。 戦争をはさんで、師とあおぐボーアとの仲もぎくしゃくするようになる部分も冷静(冷徹なくらい)に述べています。ボーアも人間だったか。
一方で盟友のパウリとの対話はあまり多くない印象でした。 それでもパウリとの仲は、同じゾンマーフェルト門下という以上に理解しあえる間柄が伺えます。 パウリとの関係は折りにふれて登場し、パウリの死の前後のやりとりではハイゼンベルクの複雑な心情と悲しみが胸を打ちます。
紛れもなく天才の一人なのでしょうが、文体からにじみ出るのは落ち着いて冷静でバランスのとれた思考の持ち主のイメージです。 第二次世界大戦前後の迷いや、母国にとどまるにいたる思考の軌跡は、誠実で信頼できる人物像で、危なっかしさが感じられない。 ナチスに世論が流れていても冷静に観察し、戦争が始まった時も戦後を見据えて行動をする。 ディラックやランダウ、ファインマンと比べると、はるかに「普通」な感じがします。 もしかすると一次大戦を経験し、その戦後でそれなりに苦労したことで身についた部分があるのかも知れません。
前半はヴァンダールンク(英語ではハイキング)中の対話が多くあります。 確かにドイツ人はハイキングが好きですが、ハイゼンベルクの健脚ぶりは常人を越えている気はします。 自然の中を歩くのを好み、音楽を好み、物理に取り組む。 研究室に閉じこもるタイプではない物理学者だったのが意外といえば意外でした。 格好だけなら真似できそうなので、ハイキングはもっと積極的に行こうかと思いました。(←なんだそれ)