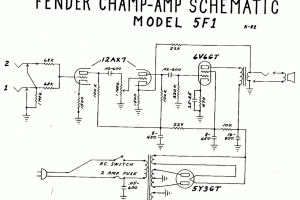(更新日: 2025年8月10日 )
国産のエレキギター・ベースブランドのフェルナンデスが倒産したニュースがXに流れて、多くの反応があったようだ。
私が最初に手にしたギターはフェルナンデスのリバイバル・シリーズのストラト・タイプ(RST50-57)だった。 フェルナンデスと言えば、俺の最初のギターなのだ。
楽器業界そのものは、一時期のブーム以外は好況とか不況とかいうわけでも無いように思うのだが、どうだろうか。 素人ながら、フェルナンデスの経営が芳しくなかった理由はなんとなく想像できる。
目次
国内メーカー全盛時代
自分の感覚だとフェルナンデスなど日本の国内メーカーが最も元気だったのは1980年代までだったと思う。 (売上げは90年代のほうが良いようだが…。)
1980年代やそれ以前は、FenderやGibsonは高嶺の花の存在で、初心者が手に取るのは国内メーカーだった。 アーティスト・モデルのコピーも国内メーカー品でそれなりのものが入手できた。 海外アーティス・モデルのコピーの領域でフェルナンデスはかなり頑張っていた(今となっては見た目重視のようにも思えるが)。
市場環境の変化
1980年代と今の大きな違いは、FenderとかGibsonとかを「普通」に買うようになったことだろう。 FenderもGibsonもラインナップが豊富になって、価格の点では以前と比べて買い難さは緩和されている。
さらに初心者向けブランドとして、FenderにはSquireがあるし、GibsonにはEpiphoneもある。 それらは堂々と”Stratocaster”,”Telecaster”, “Les Paul”モデルを名乗ることができる。
つまるところ、今どきはFenderやGibson、PRS以外の量産メーカーは「売り」が非常に難しい状況になった。 楽器店に行けば、展示されている商品のラインナップを見ると良い。 30~40年前と比較すれば、楽器店の店頭で展示されているフェルナンデスのモデルは圧倒的に減った。
国内メーカーの苦戦
フェルナンデスに限らずトーカイやグレコのストラト・タイプやレスポール・タイプを敢えての買う人は今の時代は多くない。 FenderやGibsonのモデルと差別化された点(主に演奏性の観点)の良さが分かっている人や狙って買う人だけになっている。 値段が高い価格帯では、Fender、GibsonやPRSも検討するようになるし、そうなるとネーム・バリューやブランド的にはフェルナンデスはかなり不利だ。 特に自社工場を持たないフェルナンデスなどは商品企画で強みを打ち出す必要がある。 フェルナンデスは、なるほどいくつか個性的な商品を生み出してきたが、それでも綱渡りな経営だったということではないか。
アイバニーズとの比較
一方アイバニーズは、デザインや演奏性などの点で特定ジャンルでは選択肢の筆頭に挙がる地位を確立している。 そういう点で差別化にある程度成功している。 もともとアイバニーズは独自路線のブランドであった。
アイバニーズと比較すると、フェルナンデスはユーザー視点でのブランド・イメージや方向性が掴みづらい。 そうしたブランディングや方向性付けの失敗が、今回のような結果となったのではないか。
復活はあるか
グレコやトーカイなどは本家モデルあるいは本家以上のクオリティのコピーモデルで一世を風靡した。 80年代までの日本のお家芸・製造業的な強みだったのだが、FenderやGibsonによるコピー品対策後は元気がなくなってしまった。
(ちなみに、今はストラトキャスターなどのボディ形状・ネックヘッド形状とまったく同じものを販売するにはライセンスが必要になる。 だから、コピーモデルは微妙に形状を変更している。 これはやっかいで、ネックやピックガードなどがFender・Gibsonモデルと微妙に異なるため、改造のハードルが上がる。)トーカイも一回倒産して復活している。フェルナンデスも復活してもらいたいが、道は険しそうだ。
なお私自身が初心者におすすめするメーカーはフジゲンである。
値段が手頃でクオリティが高く、また上達した後でも物足りなくなることはない。 80年代の日本メーカーの良さをそのまま受け継いでいるのがフジゲンである。 そもそもフェルナンデスやグレコのギターの多くはフジゲンが製造したものである。