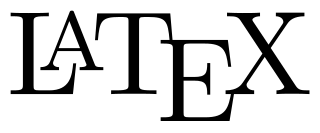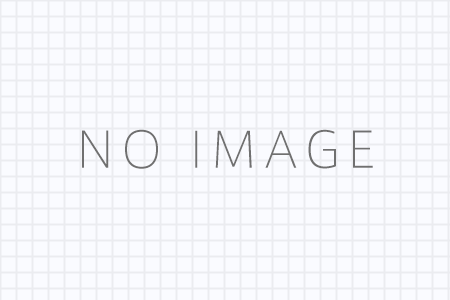(更新日: 2025年8月16日 )
LaTeXで図にテキストを回り込ませたい時がある。デフォルトでは、図の横は空白になってしまう。 テキストを図の周囲に回りこませると、ページ数を節約できたり、なにより体裁が少しかっこいい。 そういう時にはwrapfig環境を使のが良い。
目次
wrapfig環境の使い方
\usepackage{wrapfig}のようにスタイルファイルを読み込んで
\begin{wrapfigure}{position}[overhang]{width}
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{golfer.pdf}
\caption{キャプション。}
\end{wrapfigure}のように指定する。回り込ませたいテキストの前に上記の図を挿入する。
オプションの意味
オプションは以下の通り:
| 引数 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| position | 図の配置位置 (r=テキストの右, l=テキストの左, i=twosideの綴る側, o=twosideの綴る反対側) | r |
| overhang | 本文からはみ出す幅 | 10pt |
| width | wrapfigure 環境の幅 | 0.5\textwidth |
実例
以下は一例。
\documentclass{jsarticle}
\usepackage[dvipdfmx]{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\begin{document}
(第一段落)これは文章これもこれは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章文章これは文章これも文章。
\begin{wrapfigure}{r}[10pt]{0.5\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{golfer.pdf}
\caption{キャプション。}
\end{wrapfigure}
(第二段落)これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。これは文章これも文章これは文章これも文章これはこれは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章。これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも
文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章
これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。
(第三段落)これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。
(第四段落)これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。
(第五段落)これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章これは文章これも文章文章。
\end{document}上のLaTeXソースを処理すると下のようなレイアウトになる。

注意
wrapfig は長い段落や複雑なレイアウトで うまく回り込みが効かないことがある。- 回り込みが崩れるときは、wrapfig の行数指定を入れる/増やす、段落を少し長くする、overhang を減らす。
- 図の最初か最後に \vspace 少量を入れてアタリを取ると改善する場合あり。
- 大量採用前に複数ページ・二段組・脚注併用のケースを最小サンプルでビルドして検証すると安全。
類似パッケージとの比較
| 観点 | wrapfig | picins | floatflt |
|---|---|---|---|
| 主用途 | 図・表を本文に回り込ませるための定番環境(wrapfigure,wraptable) | 段落中に画像や小要素を食い込ませる(\parpic など) | 浮動体(float)を回り込み対応の浮動環境として扱う(floatingfigure 等) |
| レイアウト制御 | \begin{wrapfigure}[行数]{r/l/i/o}[overhang]{幅} で位置/幅/はみ出し/占有行数を指定 | 画像の左右・オフセット・インデントを細かく指定。直感的に“段落に貼り付ける”感覚 | 通常の浮動体に近く、ページ内での移動余地がある分、回り込みも自動調整気味 |
| キャプション・ラベル | 環境内で \caption / \label がそのまま使える | 基本は行内要素扱い。キャプションは工夫が必要(captionof など) | \caption / \label が使いやすい(ただし配置に制約が出ることあり) |
| 自動性 vs 手動調整 | “半自動”寄り。行数や overhang を指定して整える | 手動調整が中心。微調整の自由度が高いが、手間も増える | 自動性は高めだが、意図せぬ位置に逃げることがある |
| 互換性・安定感(ざっくり) | 比較的安定・広く使われる。他パッケージとの共存もしやすい部類 | 古めの設計で、文書や他パッケージ構成によっては相性差あり | 歴史が古く、相性問題の報告が多い。大規模文書で不安定になりがち |
| 二段組・リスト・脚注周り | 二段組や複雑なリスト/脚注の境界で崩れることがある(段落長に依存) | 段落の流れに密接。脚注・数式・箇条書き混在で調整が必要 | 脚注・数式・段組との相性で崩れやすいケースがある |
| 使いどころ | “まずはこれ”。論文・レポートの小〜中サイズの図に最適 | 雑誌風の紙面や小さな飾り図・著者写真など、ピンポイント装飾 | 場合により自動で位置調整してほしいとき(ただし挙動は要検証) |
| 落とし穴 | 段落が短い/改ページ近いと回り込みが割れる。行数 や overhang の見積りが外れると不自然 | キャプション・参照の一体化が面倒。テンプレ不在だと実装コスト増 | レイアウトが文書全体の浮動制御の影響を強く受け、思わぬ飛びが出る |
| 学習コスト | 低〜中:環境の引数に慣れればOK | 中:段落と箱の関係を理解して微調整 | 低:概念は簡単だが、挙動理解に検証が必要 |