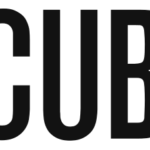10代のころに読んだはずなのに、実はまったく覚えていなかった。 今回読んでみて、10代には少し早い内容だったとは思う。
「彼岸過迄」というのは、元日から始めて彼岸過迄ぎまでに書く予定だから単にそう名づけたまでにすぎない実は空しい標題である。
とのことなので、タイトルは内容と関係がない。
内容は大きく主人公 敬太郎と、森本、田口、松本、須永と千代子との関わりで短編が連結するような形態をとっている。
いずれの短編もそれぞれ引き込まれる。停留所の章は、少しだけ探偵もの風で興味深い。 雨の降る日の章は、読後の余韻が残る。 須永の話の章は、夏目漱石らしい男女間の描き方で、読んでいて苦しくなる。
時代が違っても、男女間は単純に割り切れない部分は変わらない。 時代背景を差し引いても、似たような状況は現代でもありそうだ。 しかしこのせわしない世の中では、夏目漱石が細やかに描く複雑な感情の機微が自分達にあっても、それを見つめることなく死んでいく人も多いのではないかと思った。
久し振りに整った日本語を読んだようで、なんだか背筋が伸びる気がする。 明治時代にこのような小説が新聞に連載されていたのが信じられない。 このような日本語を現代の日本人はどれだけ読み通せるだろうか。