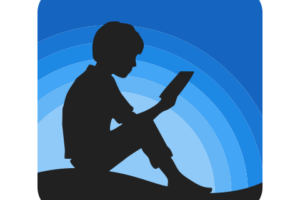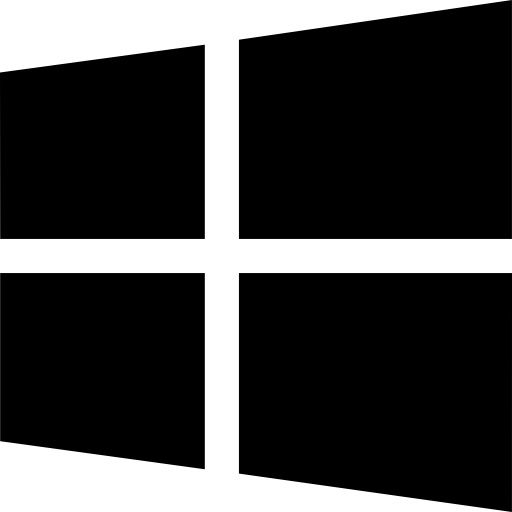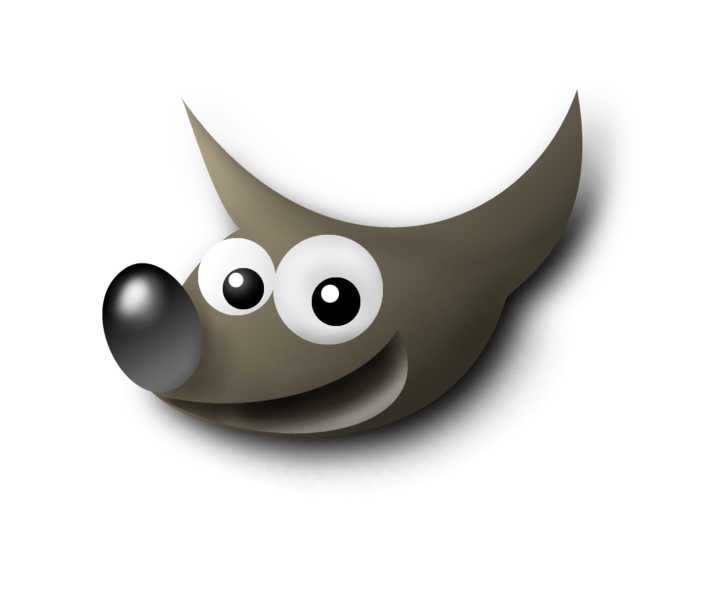目次
はじめに
今やオープンソース(以下OSS)系のアプリやパッケージは、個人利用だけでなく仕事でも欠かせないほど普及している。
しかし、定番のOSSアプリやパッケージがマルウェアに汚染されていたという例は、実はかなり多い。
そうしたOSSの汚染や本家サイト詐欺の事例と、個人ができる対策についてまとめてみた。
(なお、私自身が何か汚染を掴まされて懺悔しているわけではない。 今さらながら過去のNotepad++やAudacityの偽サイト騒ぎを知って調べてみたものだ。)

汚染されたOSSソフトウェアが配布された例
まずは、本家サイトが改竄されOSSソフトウェアそのものが汚染されていた例、詐称サイトに誘導された例のリストである:
公式サイトやミラーが改ざんされ、正規と誤信して汚染版を入手
- Linux Mint 17.3(2016年2月20日):公式サイトが改ざんされ、バックドア入りISO(Tsunami/BOT)がリンクされる。被害ユーザーに注意喚起と対処手順を告知。 (Linux Mint Blog, micahflee)
- Transmission for macOS(2016年3月4–5日):公式サイトのDMGが置き換えられ、KeRanger ランサムウェアを配布。Appleが証明書失効・対策、数千台規模に影響の報道。 (Unit 42, WIRED, ウィキペディア)
- HandBrake for macOS(2017年5月2–6日):ミラーサーバが侵害され、Proton RAT入りインストーラが配布。ダウンロード期間内の利用者に感染リスク。 (Intego, We Live Security)
- PHP PEAR(2019年1月発覚):pear.php.net上のgo-pear.pharが改ざん版に差し替え。少なくとも「過去6か月」入手分が影響の可能性。 (Rapid7, Bitdefender)
偽サイト・検索広告・タイポスクワットによる“なりすまし”配布
- VeraCrypt(2020年1月):Google広告経由の偽サイトが改ざんインストーラ(EV署名悪用)を配布。開発者が確認・注意喚起。 (ソースフォージ)
- Audacity(2021年ごろ):検索上位に出た偽サイトから入手した複数台がマルウェア感染との報告(公式のGitHubディスカッション)。 (GitHub)
- OBS Studio(2022年末〜2023年):Google広告の偽サイト経由で入手した偽OBSにより著名ユーザー(NFT God)がアカウント/暗号資産を窃取される被害を公表。 (BleepingComputer)
- RomComキャンペーン(2023年):GIMP等のOSSサイトを装った偽ページを広告で拡散し、バックドア(RomCom)を配布。地域的に標的化の被害確認。 (BleepingComputer)
- KeePass(2023年〜2025年):Punycodeドメインの偽サイトや広告でトロイの木馬化KeePassを配布。情報窃取〜ランサムウェア侵入まで確認の事例・注意喚起が複数。 (BleepingComputer, labs.withsecure.com, urz.uni-heidelberg.de)
- WinSCP/PuTTY(2024年〜継続):検索広告で偽サイトへ誘導しトロイ化インストーラを配布、ランサムウェア投入未遂/投入の事例を複数社が観測。 (Rapid7, BleepingComputer, Infoblox Blog)
- 7-Zip/VLC/Blender/Notepad++ ほか(2022–2023年):多数のOSSを装う偽ダウンロードが広告で量産。実際に情報窃取(RedLine/Vidar等)やアカウント乗っ取り被害が確認。 (BleepingComputer, threatresearch.ext.hp.com)
補足:上記は「本家の配布物そのものが差し替えられたケース」(Linux Mint/Transmission/HandBrake/PEAR)と、「本家そっくりの偽ダウンロード先へ誘導されたケース」(VeraCrypt/OBS/GIMP/KeePass/WinSCP/PuTTY/7-Zip/VLC等)が混在。いずれも正規と思い込ませて汚染版を入手させた点が共通。
すぐ実践できる再発防止チェック(簡潔版)
- 公式ドメイン直打ち(広告枠はクリックしない/見分けにくい)。
- 署名とハッシュ検証:署名者名の妥当性、公開鍵/ハッシュは別経路(GitHub・署名鍵サーバ等)で確認。
- パッケージマネージャを優先(Linux: repo/署名キー、Windows: winget/Choco、macOS: Homebrew など)。
- HTTPSとHSTS強制、リリースはGitHub等の公式リポジトリから辿る。
- 検索結果のTyposquatting/Punycode(例:ドメインの点や長音/似字)を警戒。
- 企業内はDNS/URLフィルタ+広告除去、DL用VM/サンドボックスでまず検査。
アプリ自身のアップデート機能が汚染されていた例
最近のアプリはご丁寧にアップデートを通知してくれ、なかには自動でアップデートまでしてくれる。
これは便利な機能なのだが、アップデートサーバが改竄されたり、アップデート機能そのものが改竄されている例もある。
実際に起きた「アップデート経路の汚染」事例
- CCleaner(2017年) 正規のアップデートサーバに侵入され、公式署名付きのCCleanerが改ざんされて配布。自動アップデート経由で数百万台に感染(後にAPT攻撃に利用)。
- NotPetya(2017年) ウクライナの会計ソフト「M.E.Doc」の公式アップデート機能が侵害され、アップデート経由でマルウェア(NotPetya)が大量配布。世界規模の被害に発展。
- ASUS Live Update(2018年) ASUSの正規アップデート機構がハッキングされ、バックドア入り更新が数十万台に配布(ShadowHammer事件)。電子署名も正規のものが使われていた。
- SolarWinds Orion(2020年) アップデート配布チェーンに侵入され、正規アップデートとしてトロイの木馬版が配布。世界の政府機関・企業に甚大な被害。
- Codecov(2021年) Bash Uploaderの自動アップデートスクリプトが改ざんされ、アップデート経由で数か月間にわたりトークン・認証情報が流出。
- 3CX Desktop App(2023年) 正規ビルド工程とアップデート配布サーバが汚染され、ユーザーが自動更新でバックドア入りバイナリを取得。サプライチェーン攻撃の典型例。
教訓と対策
- 「公式署名」だけでは不十分 上記の多くは正規の署名付きバイナリだったため、単に署名を検証するだけでは防げなかった。
- 多段検証
- 公式のハッシュ値や署名キーを複数経路で確認(例:開発者のGitHub+メーリングリスト)。
- OSやパッケージマネージャの仕組み(APT, RPM, winget, Homebrew など)を優先。
- アップデート経路の分離・監視
- 社内では「アップデートを直接インターネットから受け取らず、プロキシや検証サーバを介す」設計が望ましい。
IDS/EDRでアップデート通信を監視し、異常挙動を検知。
結論: アプリが「自動更新だから安全」とは限らない。むしろ攻撃者にとって格好の侵入口であり、歴史的にも大規模インシデントが繰り返されている。 ユーザー側で「正規配布元の健全性を疑う習慣」を持つことがリスク低減につながる。
パッケージ系が汚染されていた例
JavaScript系、Pythonなどパッケージ系も例外ではない。 これらも、かなり厄介な問題だと思う。
パッケージレジストリ汚染・詐称の実例
JavaScript / npm
- event-stream(2018年) 人気パッケージのメンテナが権限を譲渡 → 攻撃者が依存パッケージにマルウェアを仕込み、ビットコインウォレット(Copay)を狙う。数百万DL規模。
- ua-parser-js(2021年) 6,000万DL/月のライブラリに、盗難ツール&暗号通貨マイナーが混入(開発者アカウント侵害)。
- node-ipc(2022年) ロシア・ベラルーシ環境でファイルを削除する「抗議ウェア」を作者自身が追加し、依存していた多数のプロジェクトに影響。
- 複数のtyposquatting攻撃(継続)
expresss,lodas,crossenvなど、本物に似せた名前で悪意あるパッケージを公開 → 情報窃取やリバースシェル。
Python / PyPI
- ctx / jellyfish(2017年ごろ) 正規人気パッケージに似せた名前で不正版を登録、環境変数からAWSキーなどを盗む。
- colourama / python3-dateutil(2018年) タイポスクワットで機密情報窃取。
- 2021–2022年の大規模攻撃 数千件以上のtyposquat・マルウェア混入が一斉に報告。例:
request(本物はrequests)、urlib3(本物はurllib3)など。 - 2023年 onward: サプライチェーン攻撃 攻撃者がメンテナアカウントを奪取 → 正規パッケージにトロイを混入した事例(例:
django-toolbeltに類似する偽パッケージ)。
Ruby / RubyGems
- 2019年:rest-client 偽版 正規に似せた gem にバックドア混入、環境変数や秘密鍵を外部送信。
- 2020年:725件の悪意あるGem Typosquat名や人気ライブラリに似せたものが発見 → 暗号通貨窃取コードなど。
PHP / Composer(Packagist)
- 2019–2020年 パッケージ名のtyposquattingによる不正アップロード事例が複数。多くは情報窃取型。
- 大規模事件は少ないが「本物と見分けにくい名前」の被害が定期的に発見。
Java / Maven Central
- 2021年以降:研究者によるPoC攻撃 同名パッケージを Maven Central に登録 → 内部リポジトリから自動解決され「依存関係混乱(Dependency Confusion)」攻撃が成立。MicrosoftやApple社内環境でも実証。
- 実害事例は少ないが、企業環境では深刻なリスク。
.NET / NuGet
- 2021年以降:Dependency Confusion実証 内部専用パッケージ名と同名を NuGet に登録し、開発環境に侵入可能と証明。
- Typosquattingや情報窃取型の不正パッケージも確認されている。
共通する攻撃手口
- Typosquatting:人気ライブラリ名に似せる(例:
reqeusts)。 - アカウント侵害:正規メンテナのアカウント奪取後、悪意あるバージョンを公開。
- 依存関係混乱(Dependency Confusion):社内パッケージと同名を公開レジストリに置き、ビルドが自動で拾うようにする。
- 内部に悪意あるインストールスクリプト:
setup.py,package.jsonなどに窃取コードやシェルを仕込む。
ユーザー側の最小対策
- パッケージ名を慎重に確認(1文字違いでも要警戒)。
- 信頼できるレジストリのみ使用、内部専用はスコープ付きやプライベートリポジトリに限定。
- インストール時にハッシュ固定(lockファイル) → npm:
package-lock.json/ pip:requirements.txtにハッシュ付きで記録。 - 依存監査ツールの活用
- npm:
npm audit - Python:
pip-audit GitHub Dependabot / Snyk など
まとめると、npm・PyPI を中心に「パッケージ詐称・汚染」は日常的に発生しており、event-stream, ua-parser-js, rest-client, ctx などは実際の被害が確認された代表例。
OSSアプリ・パッケージのインストール・更新で個人ができる対策
もはやPCやスマホは、悪意を持つ者が隙あらば狙っている空間である。それは個人レベルから国家レベルまでに及ぶ。
個人利用だろうが仕事だろうが、最低限の対策をするに越したことはない。
OSS アプリ(単体アプリ)のインストール・更新対策
1. ダウンロード元の確認
- 公式サイトのドメインを直打ち(検索広告や上位結果に頼らない)。
- GitHub や SourceForge など、公式が明言している配布チャネルからのみ入手。
2. ハッシュ値・署名の検証
- 提供されている場合は SHA256 などのハッシュ値を確認。
- 可能なら PGP署名を検証(複数経路で公開鍵を取得)。
3. パッケージマネージャの活用
- Windows → winget / Chocolatey
- macOS → Homebrew
- Linux → apt / dnf / pacman など 独自ダウンロードより安全性が高い。
4. アップデート時の注意
- 自動アップデートは即適用しない → 1〜2日待ってSNS/公式で不具合報告がないか確認。
- 挙動に違和感があれば中止 → 異常に遅い、許可を要求するなど。
5. 最後の砦
- 常駐型のアンチウイルス/EDR を有効にしておく。
- 不審な挙動があればアップデート直後を疑う。
パッケージ系(npm / PyPI / RubyGems / NuGet / Maven など)
1. パッケージ名の確認
- 一文字違い(typosquatting)に要注意
-
requests(正規) vsrequest(偽) -
urllib3vsurlib3
2. 信頼できるソースのみ利用
- npm, PyPI, RubyGems など公式レジストリを利用。
- 内部利用パッケージは スコープ付き / プライベートリポジトリ を必須化。
3. ロックファイルの活用
- npm →
package-lock.json - Python →
requirements.txt/pip-tools/pip-audit - Ruby →
Gemfile.lock依存関係を固定して、予期せぬアップデートや汚染版を防ぐ。
4. 依存関係の監査
npm audit,yarn auditpip-audit,safetybundle audit- Dependabot / Snyk / Renovate などの自動監査ツールを活用。
5. インストール時の挙動確認
setup.py,install.js,postinstallスクリプトを警戒。- 不要な依存が大量に追加されていないかチェック。
6. 更新のタイミング
- 最新版にすぐ追随しない
- 重要セキュリティパッチ以外は 少し待ってから更新。
7. アカウント保護(開発者側)
- 自分が公開する場合は MFA有効化・署名必須化。
- パッケージを引き継ぐ場合は正規の手続きを確認。
共通の心構え
- 「自動=安全」と思わない → 正規アップデート機構そのものが侵害された事例あり(CCleaner, SolarWinds, 3CX)。
- 「便利さ」と「安全性」のバランス → 100%の検証は難しいが、「名前・ソース・署名確認」を習慣化するだけで被害率は大幅減。
- 企業レベルの防御(参考)
- 社内プロキシやアーティファクトリでパッケージをキャッシュ・検証してから配布。
- 監査ログを残して不審挙動を早期検知。
まとめ
- アプリ系 → 公式サイト直打ち・ハッシュ確認・パッケージマネージャ活用・アップデートはワンテンポ置く。
- パッケージ系 → 名前の確認・ロックファイル固定・監査ツール活用・インストールスクリプト警戒。
おわりに
私が使っている定番OSS系アプリも過去に汚染されていたことを知って、正直少し恐れをなしている。 定番だからこそ狙われていると考えるべきだろう。
私の場合、初めて使うアプリは勝手がわからず安易にインストールをしてしまいがちであると反省している。
GitHubなどのReleaseから直接取得することや、アップデートを急がない、など実践できることは多いと思う。