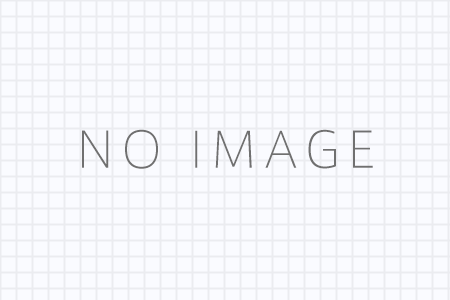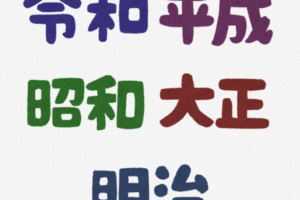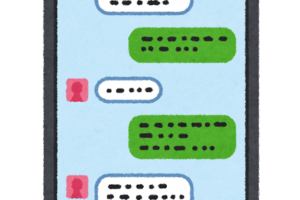(更新日: 2025年8月15日 )
NEC筑波研究所が、2020年3月末に約30年の歴史に幕を下ろすことになった。
風のうわさでNEC筑波研究所を閉じると聞いていたが、ようやくニュースでも報じられた。2020年3月末に閉鎖とある。
Twitterではあまり言及されていないようで、認知度としてはそんなものなのかも知れない。
【茨城新聞】NEC 筑波研究所を閉鎖 来年3月末 拠点集約、コスト削減NECのプレスリリースでも簡単に触れている: 2019年3月期 第3四半期決算短信[IFRS](連結)のプレゼン資料 6ページ目
かつて働いていた職場がなくなるのは、去った者でも寂しいものだ。
この機会にNECの筑波研究所と、数年間在籍していたNEC基礎研究所の歴史をおさらいしてみた。私の記憶違いもあるだろうが、大目に見て欲しい。
目次
NEC筑波研究所はどんな拠点だったのか
ロケーション
つくば市は工業団地と呼ばれる地域が8箇所あり、NECの筑波研究所は西部工業団地に作られた。
開所と閉鎖の時期
筑波研究所は平成元年(1989年)に開所している。
2020年に筑波研究所がなくなるとすると約30年の歴史に幕ということになる。 私はその半分くらいに在籍したことになる。
研究領域と変遷
NECの筑波研究所は材料研究・半導体デバイス(光通信系・LSI系)研究の拠点だった。 時期によって違いはあるが、どちらかと言うと基礎研究よりの雰囲気だったと思われる。
2000年くらいまでは光通信系の半導体デバイスの研究部隊が多く在籍していた。 LSI系のプロセス研究部も在籍していた時期がある。 基礎的な研究をする部門として基礎研究所があり、1989年から筑波研究所に移った。
2000年代の中盤からは、川崎市にあった中央研究所拠点が閉鎖された関係で、材料系の研究者が移って来た。 こうして2005年以降は、NECの材料系・デバイス系はすべて筑波研究所に集約されるような様相となった。
規模
2000年に入る前くらいは最大で300人規模の拠点だったようだ。 その後は、光通信系の研究者が大津に異動し、またLSI系の研究者も相模原などに異動し、減少した。
私が辞める2013年頃は100人を切っていたと思う。
NEC基礎研究所の概要
歴史
NECの基礎研究所は 精密工学会誌 53 (1987年)によれば昭和57年(1982年)に設立とある。
基礎研究所は2004年ごろに基礎・環境研となり基礎研究所そのものは消滅。 基礎研究所の歴史は20年ほど。
研究テーマ
上記のリンク先によれば設立の当初から材料研究が主となっている。
高温超伝導などの材料系、半導体デバイス系、第一原理計算系などの研究グループがあった。 これらの多くは、どこかしら半導体事業との関連を持っていた。 音声認識のグループもあったが、こうしたグループは情報系の研究所に移っていった。
よく知られた成果
基礎研究所のよく知られた成果はカーボンナノチューブと量子ビットの二つだろう。 この二つはNECの筑波研究所/基礎研究所発の輝かしい成果であったと言える。 ただ、これらがNEC本体の業績にどれだけ貢献したか、というのは意見が分かれるところではないか。
NECの材料・デバイス系研究の変遷
基礎研究所や筑波研究所という視点ではなく、NECの材料・デバイス系の研究について見てみよう。
2004年以降は材料・デバイス系の研究所の名前が目まぐるしく変わる
私は約5年間を基礎研究所の研究者として在籍したが、その後も職場の拠点は変わっていない。 その一方で組織の名称が目まぐるしく変わった。 基礎研究所の後は、基礎・環境研究所、グリーン・イノベーション研究所、スマートエネルギー研究所といった具合に、数年の単位で研究所の名前が変わった。
この変遷は、会社の戦略というよりは、むしろ旬と思われる領域に研究を集中していかざるを得なかった背景がある。 私が在籍した1998年から2013年は半導体デバイス領域からナノテクへ、そして環境技術(燃料電池やリチウムイオン電池)へ移行していた時期だ。 エレクトロニクスから環境技術へという流れが読み取れるが、これは会社が積極的に戦略として仕掛けていたとは言いがたい。 この場合、短期間に組織名がころころ変わることにポジティブな意味はない。
半導体部門の分社化
NECの材料・デバイス系研究の変遷を考えるうえでは、NECの事業状況の変化を知ると良い。
2002年に半導体部門をNECエレクトロニクス社に分社化。これにより連結内とは言え、半導体系の受託研究費用が入りづらくなった。 研究予算が入りづらくなったため、この辺から半導体・材料系の研究所全体の雲行が怪しくなる。
この時期から半導体や超伝導体研究ではないテーマ、例えばエネルギー関係(燃料電池)のテーマを立ち上げて、これも国プロジェクトに応募するようになった。
半導体部門をルネサスエレクトロニクスへ統合: エネルギーデバイス(リチウムイオン電池)系の研究に集中
2009年は決定的な出来事が起こる。
2009年に半導体部門をルネサスエレクトロニクスに統合する方針が出されて、研究所を含めて大幅な人員整理がされた。 大津の研究所は閉鎖、相模原の研究所も半導体系は閉鎖、相模原の半導体工場も閉鎖。 移籍組と残留組に分けられ、残留組の半導体系人員はエネルギー関係に移ってきた。 この時期の社内は暗い知らせばかりだった。
2009年の大規模な閉鎖に比べれば、筑波研究所の閉鎖はかなりマイルドな動きだったのかも知れない。
エネルギーデバイス関係事業の終焉
2009年前後からNECはエネルギーデバイス事業に力を入れたようにも見えたが、それも長くは続かなかった。 自動車向け電極事業、家庭用蓄電事業などのエネルギーデバイス系の事業も2015年ごろから終息に向かう。 私はすでに退職していたため、この辺りの動きは外からしか分からない。
こうなると、材料・デバイス系の研究領域は社内出口がまったくない。 筑波研究所の閉鎖も、NECの事情としては必然だったと言えよう。
所感
2002年のNECエレクトロニクス社に分社化の時点から、材料・デバイス系および周辺の研究活動がたどる道はほぼ決まっていたと思う。
結果として、それを20年もかけて終結させたことになる。
多くの研究者は配置転換(テーマ替え)した。 このような時に研究者を切らなかった経営姿勢は意見が分かれるだろう。
幹部が研究者が失職しないように奔走したのは知っている。 しかし、まだまだ若手研究者が多かった時期にこの手の延命措置を講じたのが良かったのかどうか。 結果的に、まだ希望があるように思わせて飼い殺しのような状態になった面はあると思う。
辞めていった人は多いが、一方でやめるタイミングを逃した人もいただろう。 しがみついても研究所の状況が改善する兆しすら見えないのに、自分から踏み出せないということなのかも知れない。 会社から最後通告を出してあげるのも思いやりではないだろうか。