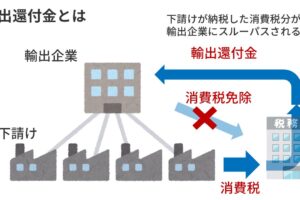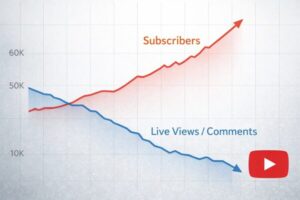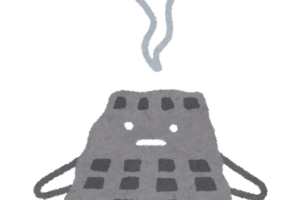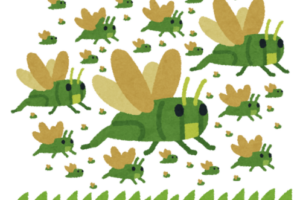(更新日: 2025年8月9日 )
目次
果たしてまともな経済学はあるのか
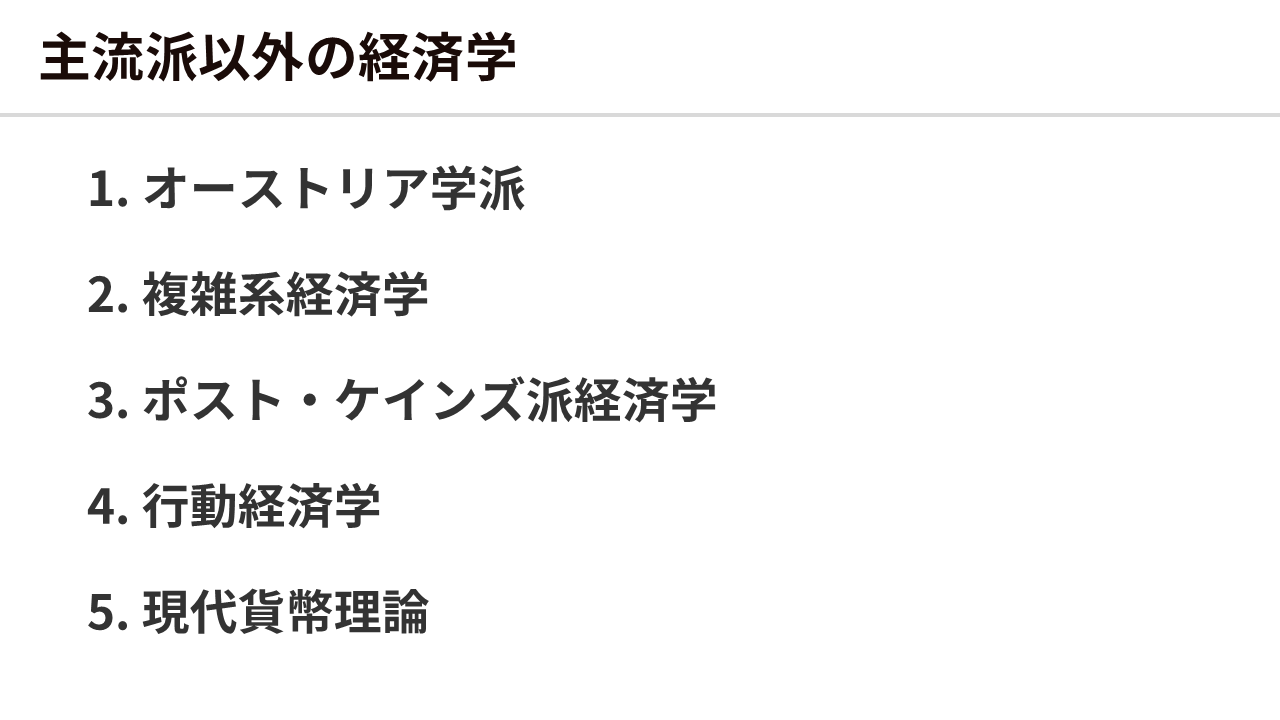
「このような学問ではないものを学問っぽく見せる態度を改善しようとする動きは経済学者達の間ではありますか?つまり、マクロ経済学や主流派とは異なる、より健全な学問を志向する人たちの活動はありますか?」
主流派とは異なる健全な経済学の動きはあるのか?
結論から言えば、マクロ経済学や主流派経済学の問題点を指摘し、より実証的・現実的なアプローチを志向する経済学者たちの動きは存在します。彼らは、数学的モデルによる過度な抽象化や、予測の不確かさを無視する態度に疑問を抱き、より現実の経済現象に即した学問としての経済学を目指しています。
以下、主流派とは異なるアプローチを取る経済学の潮流や、それを推進する学者たちを紹介します。
1. オーストリア学派(Austrian School)
→ 主流派マクロ経済学の数学モデルを否定し、「人間行動」の理解を重視する
- 代表的な経済学者:フリードリヒ・ハイエク、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス
- 数学や統計に基づくモデルではなく、**「人間の行動や意思決定を理解することこそが経済学の本質」**と考える。
- 市場の動きは計算可能な数学モデルではなく、個々の人間の選択と創発的な秩序の結果であると主張。
- 主流派が「経済を制御できる」と考えるのに対し、オーストリア学派は「経済の未来は予測不能であり、計画的な介入は害をなす」と考える。
👉 批判点
- 実証データをあまり重視しないため、「学問としての厳密性が足りない」と見なされることがある。
- 中央銀行の役割や金融政策を否定的に見るため、政治的に受け入れられにくい。
2. 複雑系経済学(Complexity Economics)
→ 経済を機械的なシステムではなく、生態系のような「進化するシステム」として研究する
- 代表的な経済学者:ブライアン・アーサー、エリック・ベーリンジャー、ジョン・ホランド
- 従来のマクロ経済学が「均衡」を前提とするのに対し、「経済は常に進化し、不均衡が標準である」と考える。
- 数学的モデルを使うが、それを固定されたルールではなく、「進化する相互作用のシミュレーション」として扱う(エージェント・ベース・モデリングなど)。
- 金融危機のような「非線形の現象」を説明しようとする。
👉 批判点
- まだ発展途上の分野であり、統一された理論が確立されていない。
- 予測の精度が向上したわけではないため、政策立案への影響力が弱い。
3. ポスト・ケインズ派経済学(Post-Keynesian Economics)
→ ケインズの思想をより厳密に発展させ、「貨幣の役割」や「不確実性」を重視する
- 代表的な経済学者:ジョーン・ロビンソン、ハイマン・ミンスキー、スティーブ・キーン
- 主流派マクロ経済学が「市場均衡」を前提にするのに対し、「市場は本質的に不安定であり、均衡に向かうことはない」と考える。
- 「信用の創造」と「金融の不安定性」が経済の根本問題であると強調(ミンスキー・モーメント)。
- 金融システムがどのようにバブルと崩壊を引き起こすかを研究し、リーマン・ショックを事前に警告した経済学者もいる(例:スティーブ・キーン)。
👉 批判点
- 「不確実性が支配する」という前提が強すぎるため、政策提言が難しい。
- 政府介入を支持する傾向があり、自由市場を重視する立場からは批判される。
4. 行動経済学(Behavioral Economics)
→ 「人間は合理的に行動する」という主流派の前提を否定し、心理学を取り入れる
- 代表的な経済学者:ダニエル・カーネマン、リチャード・セイラー
- 主流派は「人間は合理的な意思決定をする」と仮定するが、行動経済学は「人間はバイアスを持ち、非合理的に行動する」と考える。
- 実験とデータに基づき、現実の人間の意思決定を分析。
- 金融市場のバブルや消費者行動の非合理性を説明できる。
👉 批判点
- 「人間の非合理性」を説明するのは得意だが、明確な政策提言にはつながりにくい。
- 経済学というより、心理学寄りの学問と見なされることもある。
5. 現代貨幣理論(MMT, Modern Monetary Theory)
→ 「政府は財政赤字を恐れるべきではなく、通貨発行によって経済を安定させるべき」と主張
- 代表的な経済学者:ステファニー・ケルトン、ランダル・レイ
- 「政府は自国通貨を発行できるため、財政赤字は問題にならない」と考える。
- 「税金は支出を賄うためではなく、インフレを調整するためにある」と主張。
- 「財政緊縮は不況を悪化させる」という反主流派の立場を取る。
👉 批判点
- インフレのリスクを過小評価していると批判される。
- 実際の政策への影響力はまだ限定的。
結論:主流派とは異なるアプローチは確かに存在する
現在の主流派マクロ経済学(新古典派やニューケインズ派)は、数学モデルを多用しながらも現実の経済を正確に予測できないという問題を抱えています。そのため、こうした問題を批判し、より現実的な経済学を志向する動きは確かに存在するのです。
ただし、これらの反主流派経済学も一枚岩ではなく、それぞれ異なる方向を向いているのが現状です。
- オーストリア学派 → 市場の自発的秩序を強調し、政府の介入を否定
- 複雑系経済学 → 経済の進化的・動的な側面を研究
- ポスト・ケインズ派 → 金融不安定性や信用創造を重視
- 行動経済学 → 人間の非合理性を研究
- MMT → 財政赤字の肯定とインフレ管理の新しい視点
主流派経済学の問題に疑問を持つなら、これらの異なる経済学を研究し、それぞれの強みや弱点を比較することが重要です。
「これらの主流派とは異なる経済学のアプローチのなかでも科学になり得るものはありますか?また、その理由は何でしょうか?」
主流派とは異なる経済学のアプローチの中で「科学になり得るもの」はあるか?
結論として、科学の条件(再現性・予測可能性・反証可能性)を満たす可能性がある経済学のアプローチは存在しますが、完全に「科学」と言い切れるものは少ないです。ただし、以下のようなアプローチは比較的科学的な方向に進んでいます。
1. 複雑系経済学(Complexity Economics)
✅ 科学になり得る可能性:高い
❌ 限界:まだ統一理論が確立していない理由
シミュレーションを使い、経済現象を「再現」できる
- 複雑系経済学では**「エージェント・ベース・モデリング(ABM)」**を用い、個々の経済主体(消費者・企業・政府など)が相互作用することで市場の動きをシミュレートする。
- 例えば、**「バブルがどのように発生し、崩壊するか」**をコンピュータ上で再現できる。
- これは物理学の「流体力学シミュレーション」などと類似しており、再現性のあるモデルになりつつある。
経済の非線形性(カオス的振る舞い)を考慮している
- 主流派のマクロ経済学は「市場は均衡に向かう」と仮定するが、現実には市場は不安定。
- 複雑系経済学では、経済を「動的システム」として扱い、非線形な変動をシミュレーションする。
- これは物理学や生態学で使われる手法と似ており、科学的な発展が期待できる。
👉 複雑系経済学は「経済を物理システムのように扱う」という点で科学に近いが、まだ理論が統一されておらず、完全な科学とは言い切れない。
2. 行動経済学(Behavioral Economics)
✅ 科学になり得る可能性:高い
❌ 限界:予測可能性は低い理由
実験やデータに基づく研究が可能(再現性あり)
- 伝統的な経済学は「人間は合理的である」と仮定するが、行動経済学は心理学の実験を用いて、人間が実際には非合理的な判断をすることを示す。
- 例:「損失回避バイアス」(人は利益を得るよりも損失を避ける行動を取る)
- この種の研究は、実験室やフィールド実験で繰り返し検証できるため、科学に近い。
データ分析によって「法則性」を発見できる
- 例えば、「ナッジ(Nudge)」理論では、人間の行動を特定の方向に導く手法が確立されている(例:年金加入率を上げるための選択肢の提示方法など)。
- データ分析を基に「この条件なら90%の確率で特定の行動をとる」などの予測ができる。
👉 行動経済学は実験とデータに基づくため、心理学や神経科学に近い科学的アプローチと言える。ただし、個々の人間の行動には予測不可能な要素も多く、経済全体の未来を完全に予測するのは難しい。
3. ポスト・ケインズ派経済学(Post-Keynesian Economics)
✅ 科学になり得る可能性:中程度
❌ 限界:反証可能性が弱い理由
ミンスキー・モーメント(金融不安定性理論)は事例に基づく実証研究が可能
- **「金融市場は本質的に不安定であり、周期的な危機が起こる」**という仮説は、過去の金融危機(リーマン・ショックなど)とよく一致する。
- これは歴史的データを使った実証研究が可能であり、ある程度の科学性を持つ。
実証分析は可能だが、厳密な数式モデルが弱い
- 主流派の経済学は「数学モデル」を重視するが、ポスト・ケインズ派は歴史や制度の影響を重視するため、数式モデルの一般化が難しい。
- 例えば、「政府支出の拡大は景気回復につながる」という理論は、時代や国によって結果が異なるため、物理学のような普遍的な法則にはなりにくい。
👉 ポスト・ケインズ派は歴史とデータを重視するため科学に近いが、厳密な理論体系が不足しており、完全な科学とは言いにくい。
科学になりにくいもの
❌ オーストリア学派
- 再現性がなく、数式モデルを使わないため、科学的検証が難しい。
- 「市場は計算できない」という立場を取るため、予測可能性がない。
- 「政府の介入は常に悪」という価値観が前提になっているため、反証可能性が弱い。
❌ MMT(現代貨幣理論)
- 「財政赤字は問題にならない」という主張は、特定の政治的立場と結びつきやすく、科学的議論よりも政策論争になりがち。
- 理論としての一貫性はあるが、「インフレの管理が本当に可能か?」という部分で実証が不足。
結論:どの経済学が科学になり得るか?
経済学派 科学的か? 主な理由 複雑系経済学 ✅ 高い シミュレーションで再現可能、非線形現象を説明 行動経済学 ✅ 高い 実験とデータに基づく、心理学的アプローチ ポスト・ケインズ派 ⚠️ 中程度 歴史とデータ重視だが、数式モデルが弱い オーストリア学派 ❌ 低い 再現性がなく、数式モデルを使わない MMT ❌ 低い 政策理論に近く、実証データが不十分 👉 結論:複雑系経済学と行動経済学は、経済学の中でも特に科学に近いアプローチを持っている。
- 複雑系経済学は「物理学のようなシミュレーション」
- 行動経済学は「心理学・実験データに基づく」
完全に物理学のような「厳密な科学」にはならないが、再現性・予測可能性を高める方向に進んでいるため、将来的にはより科学的な経済学として発展する可能性がある。