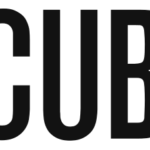太宰治の「待つ」(太宰治 待つ | 青空文庫)についての論文があった(太宰治「待つ」論–「京都帝国大学新聞」との関連を踏まえつつ | CiNii Research)。とても興味深く、読み方としてはこれが太宰治の意図をよく汲み取っているように思える。
もともと「待つ」は京都帝国大学新聞から依頼された短編(コントと書かれている)で、実際には京都帝国大学新聞の誌上では未発表で原稿を返却されている。 それが作品集『女性』の最後に収録されることになる。
上記の論文では、戦争開始後の京都帝国大学新聞の記事の状況の変化を踏まえ、「待つ」に書かれているテーマについて論じている。 作品集の『女性』に入れたのは太宰自身の願いであった。その「願い」の意図も想像しながら読むと「待つ」のテーマもより浮きあがってくる。
毎日列車に乗り働いて帰ってくる毎日の人々とは違い、買い物の終りにただその人々を眺めながら「もやもや」しながら誰か・何かを「待っている」。 今よりずっと全体主義的な雰囲気の戦時下での異質な存在。
このように「私」は国民が一丸となることを強制された「大戦争」のもとでも、一丸となるべく人々の間に入り交ろうとはしない。 そしてそうした国民と距離を置いた自分の行動に対して、「なんだか頼りない気持」になると感じながらも、「私」は決して「ここ」にいること、すなわち「待つ」ことをやめようとはしないのである。
「待つ」ことをやめない「私」は、最後に自信を持って決意表明の如く、右のことばを「あなた」に伝える。「私」は、この物語が終わった後も、やはり時流の乗ることなく「毎日、毎日」待ち続ける「二十の娘」のままでいるのである。その証拠に「いつか私を見掛ける」と言うのである。
自分は最初に読んだ時は最後の部分の意味が良く分からなかった。 最後にどこか自信のありそうな一文が急に出てきたように思えたものだ。
この短編を京都帝国大学新聞に掲載しなかった編集者も、当時の雰囲気下でこの短編の違和感を感じたに違いない。
世の中を支配している大きな雰囲気の動きを知りながら、その動きに乗らない自分を「待つ」と表現した。 そして、それを当時は自己主張が難しかったであろう女性の独白にする。ロックすぎる。 この短編は自分の超お気に入りのひとつだ。