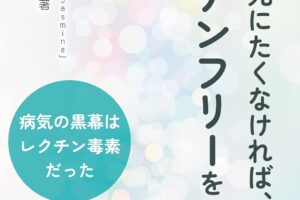(更新日: 2024年8月25日 )
この手の話は批判もあるのを承知で読んでみた。
巻末に訳者による解説があり、これが端的にまとめられている。 てっとり早く把握するうえでもこの解説を先に読んでも良い。
この本の趣旨は、かなり雑にまとめると、人類の歴史と食のパラダイムシフトを考察し、人間の食への適応性と現代の問題について述べていると言える。 スケールの大きい話である。
人類の歴史は長い狩猟の時代から農耕へ、農耕から食品工業への推移、新大陸産の新しい『食物』、農耕そのものの『近代化』『効率化』などにまとめられる。
人類が摂取できる食物は、長い狩猟時代に体得された植物の毒素(レクチン)に対する耐性がベースになっている。 しかし、農耕で作られるようになった穀物などのレクチンへの耐性はない。
新大陸原産の野菜などに対しても耐性がない。
牛の突然変異によりレクチンのように作用するカゼインを含む牛乳が広く飲まれている。
人間は人間の身体だけで生きていない。肌の表面、腸内の表面などにいる微生物たちとの共生で生きている。
基本的に腸内の微生物のはたらきが体調不良や免疫系の不調につながっている。 「栄養があるもの」と摂取しても腸内環境を破壊すると、吸収もされないし、炎症をおこしてしまう。
脂肪があるところは、体内の非常事態になっている箇所で炎症している。
などなど、なかなかに刺激的である。
個人的に一番ショックだったの抗生物質に関する話。 家畜は抗生物質を混ぜた飼料で飼育されているので、肉も抗生物質が混入している。 抗生物質は腸内の住民にも無差別攻撃をするので、抗生物質で飼育された家畜の肉も推奨されていない。 幸い、イオンでは抗生物質を入れない飼料で飼育した肉を売っているので、気になる人はイオンを探すと良いかも知れない。
後半は腸内の環境を回復させる食事法やプログラムがある。 この食事法をまともに実践できるかどうかは、覚悟次第のように思う。 本書内でも書かれている「何を食べないかが重要」とのことなので、『食べてはいけない「ジャスト・セイ・ノー」食品リスト』の食品を避けるところから始めてみようかと考えている。
ほぼ毎日摂っていたヨーグルトや牛乳はやめているが、お通じはかわらず、顔の脂は改善した気はする。 あと、にんにくは良いと書いてあるが、食べすぎると殺菌力が強すぎてお腹を壊す(実際壊した)。 いずれにしても、何を食べない(食べた)時にどのように自分の身体が変化するかを気にするのが重要そうだと思った。
蛇足ながら、もともとのきっかけは下の動画。
これはレクチンと関係なく、砂糖を1年間やめてみたらアレルギーなどの不調が改善した(性格まで変わったという)体験について述べた人の話だ。
自分はこの話に説得力を感じたので、自分も砂糖をとるのをやめてみた。 砂糖をやめるのであれば、パンもやめるのが良かろう。 なぜなら好んで食べていたバターロールなどは砂糖が入っている。 そう言えば「グルテン・フリー」というムーブメントもあったなと辿りついた。 じゃあ、小麦粉もやめてみるか。 脳腸相関という言葉も、この本の前に知った。
この本では砂糖はまったく薦められていない。小麦粉もしかり。