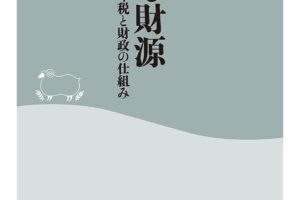(更新日: 2025年8月7日 )
目次
はじめに
どんぶり勘定事務所の「国債と税とお金の真実」が分かりやすい。
MMTで言うところの「貨幣」の説明が最もキモになるのだが、ここが一番直感的に分かりづらい。
どんぶり勘定事務所の神田氏は簿記で説明してくれている。簿記に慣れている人はこれが分かるのだと思うが、自分のように簿記に慣れていない人はどう理解するのが良いだろうか。
神田氏の説明では
- 国債はお金そのもの。借金ではない。(なぜなら返してないし、返さなくても問題ないから)
- 「お金」は貨幣と預金の二種類で理解する
とある。
国債をポイ活で理解する仮説
ならば、国債をポイ活で理解するとどうだろうか。つまり「国債 = 国から銀行に付与するポイント」と理解できないだろうか。
国債は期間があるから、「国債 = 利用期間があるポイント」。
現金以外の決済はポイントで行うイメージ。これはカード決済や銀行間での振込をポイントのやりとりで理解する。
国債以外の通常のポイントは利用期間がない。
また、銀行ではポイントを現金に交換できる。
国債の償還期限が来たら、利用期間を伸ばしたポイントに置き換える。これが国債の借り換えのイメージ。 「ポイント」だから「返す」という概念はない。これが一番イメージが近いように思われる。
こんな素人考えを図にするとこんな感じだろうか。

ChatGPTによる解説
『近代貨幣理論(MMT)の貨幣は、実際の貨幣の流通をよく説明できると思いますが、直感的に理解しづらく感じます。MMTの貨幣を現金と政府のポイントシステムに分けて理解することは可能でしょうか。ここで言うポイントとはAmazonのポイントや日本のTポイントのようなものです。国債は使用期限があるポイントを銀行に付与するようなイメージです。』
とても興味深い視点です。「近代貨幣理論(MMT)の貨幣を、現金と政府のポイントシステムに分けて理解する」というアプローチは、直感的な理解を助けるうえで有効です。MMTでは、貨幣の本質を「国家が発行し、その回収手段として税金を課すことで価値を持つもの」と捉えます。この構造は、実際のポイントシステムに似た側面を持っています。
以下に、MMTの考え方とポイント制との対応を図式的に説明してみます。
MMTにおける貨幣のイメージ
概念 MMTでの意味 ポイントシステムでの類比 貨幣 政府が発行する通貨(例:円、ドル) 企業が発行するポイント(Amazonポイントなど) 通貨の価値 税の支払い手段であることにより生じる 商品やサービスと交換できることにより生じる 政府支出 政府が貨幣を経済に注入する(給付金など) ポイントを顧客に付与する(購入時の還元など) 税金 政府が貨幣を回収する手段 ポイントを「使用」して消滅させる手段 国債 政府が将来の税収担保に貨幣を一時的に吸収する 有効期限付きポイントや前払いポイント インフレ抑制 税金や国債で市場の貨幣を吸収 ポイント利用制限で利用をコントロール 国債=有効期限付きポイントという比喩について
この比喩も面白い視点です。たとえば、次のように考えることができます:
- 国債の発行: 政府が経済に貨幣(信用)を供給した後、インフレを抑えるために国債を発行してその一部を市場から吸収する。
- ポイントの例: Amazonが「期限付きポイントキャンペーン」で一時的に購入を促し、その後失効(回収)させる。
MMTでは、国債発行は政府の支出のためにお金を集める手段ではなく、信用・金利政策の一環とされます。つまり、「支出→国債発行」の順です。ポイント制度と重ねると、「ポイント発行→ポイント回収・失効」というサイクルに似ています。
現金とポイントの2重構造でMMTを理解する
- 現金=即時に使える政府通貨(ベースマネー)
- ポイント=政府が付与する信用(将来使える・償還可能)
このように考えると、
- 現金は流通してすぐ使えるお金、
- 国債(や準貨幣)は、条件付きの使い道や将来の償還を伴う「ポイント」のようなものである、
といった構造が見えてきます。
結論
MMTの理解において、「政府貨幣=現金+政府ポイント」という分け方は、実務的な感覚を持つ人にとって非常に直感的かつ有効な理解方法です。特に企業のポイント経済に慣れている人なら、税による回収や国債による調整の意味が掴みやすくなります。
必要であれば、この比喩を使った図解もお作りできますが、どうされますか?
おわりに
素人の思い付きなので、瑕疵はいっぱいあると思う。
何かのきっかけになれば嬉しい。単にそれだけである。