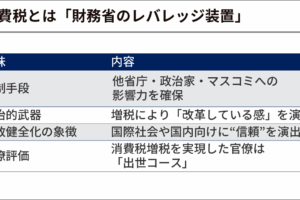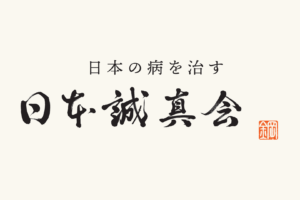(更新日: 2025年8月5日 )
2025年の参議院選挙における日本誠真会の選挙戦を振り返ってみたい。
目次
政策が分かりづらい・日本誠真会の売りは何か
政策一覧は選挙戦に入るまで完成せず、それまでは有志が個別に作成していた。 街宣でも政策よりも、現政権・現政策の批判や精神論が多く、何をやってくれる政党なのか説明しづらい。
保守系の政党は、参政党・百田日本保守党・NHK党・日本誠真会・日本改革党など投票の選択肢がいくつかある。 政党の政策比較でも分かるように、参政党・百田日本保守党・日本誠真会の政策はどれも似かよっている。 こうなると知名度が高い政党に票が取られる流れは止められないだろう。
そうした不利な状況下で、「日本誠真会を投票先として選んでもらう理由」がとても弱いと思う。 言い換えると「参政党ではダメなの?」という問いに答えるのが難しい。
参政党ではダメで、日本保守党ではダメで、日本誠真会が良いという人もいるが少数だろう。
3年前とは違う
3年前の参議院選挙は参政党が初挑戦した選挙である。この時とは状況が大きく異なる。 この時は保守系は参政党以外になく、参政党あるいは我慢して自民党に投票するくらいの選択肢しかなかった。
それに比べて、現時点では上記のように保守系の政党が複数あり乱立している状況である。 3年前に参政党が議席を獲得したような状況の再現は簡単ではないだろう。
とにかく全ての準備が遅い
とにかく準備が遅い。2025年7月の投票に対して、党の旗揚げが2024年10月、党員募集が2024年末、候補者の選定はぎぎりぎりまで決まらなかった。
ポスターなどのボランティア募集も公示前後でバタバタになった。
このように党運営が遅れていながら、党首はマーチを作曲したり、ピアノ(キーボード)の練習をするなど、意味が分からない。
運営の目論見の甘さ
今回の日本誠真会の一連の動きは、時間軸以外は参政党が3年前に参議院に挑戦した際の動きをなぞっている。 3年のビハインドがあることを考慮せず、しかも準備がほとんど後手にまわってしまい、目論見の甘さが露呈したように見える。
「二刀流」の弊害
二刀流というのは、議員だけではなく、本業を別に持つという意味で使っている。
これは日本誠真会の方針でもあると思うが、当然ながらデメリットもある。 片手間で政治活動をするのだから、どうしてもスピード感に劣るし時間が足りない。 何よりも、退路を断った候補者と比べて圧倒的に覚悟が弱くなる。
片手間でやるというなら、準備期間を長めに確保しておくのが普通の考え方だ。 日本誠真会はそういう感覚が大幅にズレていたと思う。 それが準備の遅れになったのだと思われる。
各候補者は本気で当選したいのか?
日本誠真会の候補者は、他党に比べて熱量をあまり感じられなかった。 たとえば参政党の候補者は必死さが伝わる。 本気で議員になる熱意が伝わる候補と、伝わってこない候補とどちらに投票したいだろうか。
「吉野敏明を国政に送り出すため」が目的であることは理解するにしても、本気で当選する気があるなのか分からない候補者がいたように思えた。 「特攻」と称して落選前提で候補者を立てていたせいなのか、各候補者の切実さや必死さが伝わってこない。
終わりに
かなりのお金を集めことはできたのに、準備が遅く、目論見が甘いままで参議院選挙に臨んだという、お粗末と言って良い運営を目の当たりにした。 このような言い方は反発があるだろうが、参政党のやり方を真似していたが、上手くまわせなかった。
吉野敏明氏は弁がたつ一方で、実務的な能力、戦略的な思考という点で非常に疑問を感じざるをえなかった。 「嘘をつかない」などは真偽を確かめようがない。方針転換は嘘でもないし、柔軟に対応することのほうが重要だと自分は考える。 柔軟性がなく、戦略らしい戦略も立てない人に日本の総理が務まるだろうか。
ということで、今回の選挙で日本誠真会の党員をやめることにした。 日本誠真会には期待していたのだが、日本誠真会でないとダメという理由が見付からない。 今となっては参政党を支持しても良い、そのほうが現実的であると考えが変わった。
自分の考えと政策が少しくらいハズれていても、似た政党に国会で勢力を増やしてもらうほうが建設的だと自分は思う。