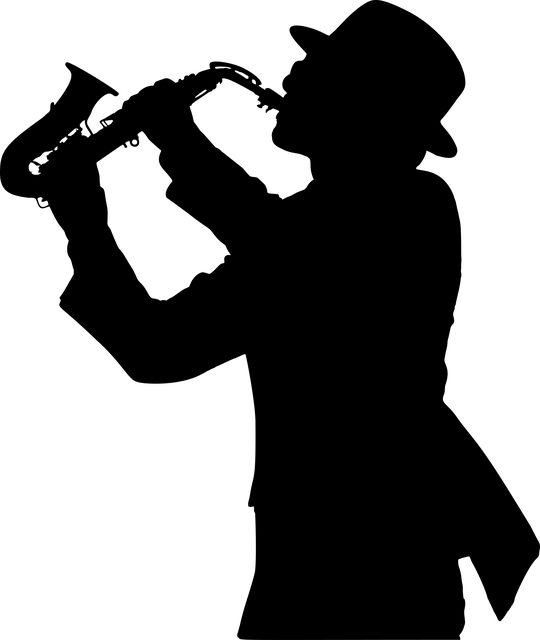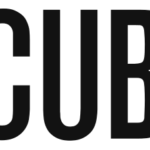(更新日: 2022年4月11日 )
インタビューをもとにした帝王マイルス・デイヴィスの伝記です。 なにかと伝説が多いマイルスですが、この本はかなり本当の姿を伝えているのでないでしょうか。
音楽へのあくなき追求の一生は感動的です。 マイルスの人生がジャズの歴史と言っても過言ではないですから、これを読むだけでもビバップからモード、フュージョン・クロスオーバーに至るムーブメントの歴史を知ることができます。あらためて「帝王」たる所以を知った思いです。
一方で、そういう意味ではいわゆるストレート・アヘッドなジャズは60年代くらいで止まってしまっているという見方もできます。 音楽的な興味を拡大していくマイルスに共感を覚えるひと、ついて行けないひとと分かれるかも知れません。
実はシャイで気遣いができる人というのは少し意外でしたが、比較的裕福な家で育ち、色んなミュージシャンにかなりかわいがられてアーティストとして成長してきたことを読むと分かる気もします。
若いころのマイルスは「研究熱心だった」と評する先輩ミュージシャンが多く、なるほどです。 フレーズやコードの響きについても先輩ミュージシャンに教えを請うて自分なりに消化して前進していく若者として見えていたようですね。
トランペットの技術そのものはディジー・ガレスピーのようには吹けないなど悩みはあったように思えますが、それを逆手にとって独自のスタイルを確立していった部分は、実はあまり認識されていないのかも知れません。
60年代以降はかなり若いミュージシャンと演奏していますが、自分から探すよりは他の人の推薦を受けた人を自分で聴いて判断するスタイルだったようです。 多くは自分の活動のためにマイルスのバンドを退団しているように読めました。
考えてみれば、マイルスのバンドを経てその後影響力のあるグループを結成したミュージシャンは多くて、マイルスのほかにこういう人はいない。 70年代のクロスオーバー系ではウェイン・ショター、ジョー・ザヴィヌル、ハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレット、トニー・ウィリアムス、ジョン・マクラフリンなど、錚々たる面々ですね。 80年代以降はマイク・スターン、ジョン・スコフィールド、マーカス・ミラーあたりが筆頭でしょうか。
この本を読んでひしひしと感じるのは、若いころからマイルスがトランペッターというよりは常に一段上の視点で創造しようとしてきた姿です。 この本では「リリシズム」と表現されていますが、マイルスが求めていたのは派手に吹きまくるセッション的なものではなく、より繊細な音楽を目指していたようです。 その手段がミュートであったり、それがバラード系で際立つというわけです。 年齢を重ねても「枯れ」とは無縁で、鋭さを失わない繊細なプレイを貫いてきたのが、ほかのトランペッターと受ける印象が違う理由だったのだと、いまさらながら理解できました。
ぼくが持っていた種々の疑問も瓦解しました:
- ギル・エバンスとの一連の作品「クールの誕生」「ポーギーとベス」「スケッチ・オブ・スペイン」と他のコンボ作品とのマイルスのなかので整合性
- いかにも荒削りで上手くなかったコルトレーンを使っていた理由
- コルトレーンが一回退団して復帰した背景
- キャノンボール名義でありながら、実質マイルスが仕切っていたと言われる「Somethin’ Else」がなんとなくマイスルの作品っぽく感じられなかった理由
- いわゆるモンクとの「喧嘩セッション」の本当のところ
- プレステージ時代のクインテットとコロンビア時代のクインテットの方向性の背景
- サックス奏者の入れ替わりが激しかった背景
- 60年代マイルスがなぜ電化していったのか
- 一回引退した背景と復帰するまでの実際
- 80年代以降のマイルスの考えていたこと
- 晩年のマイルス作品の裏側
「フリー」なムーブメントに対するマイルスのインタビューも興味深い。 「コルトレーンやオーネットはやり方が良くない」と言ったらしく、このあたりがコルトレーンのフリー系とマイルスのフリー系の演奏の印象の違いかなと腑に落ちる気はします。
晩年のレコーディングについても記述が多く、ぼくが誤解していた部分もありました。 マイルスの音楽に興味があるなら、読んで得るものは多いでしょうし、マイルスのアルバムの聴き方が大きく変わると思います。 ジャズ・ファンでマイルスに興味がない人はいないと思いますが…。