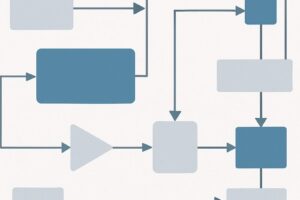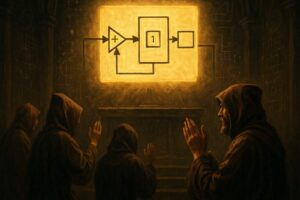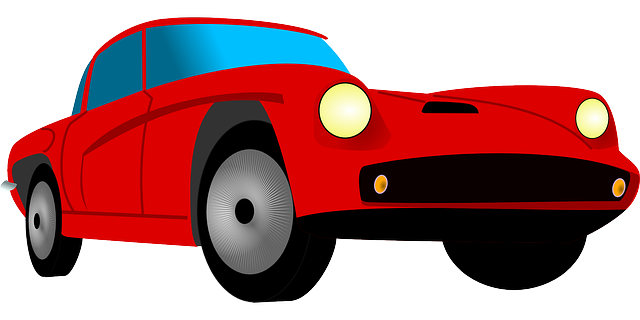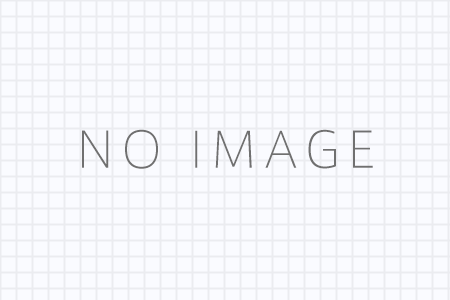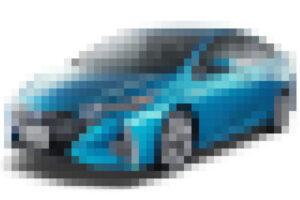目次
はじめに
MAZDAのCX-60について興味深い動画を見た。 クリーンディーゼルのクルマCX-60のエンジンについてかなり突っこんだ指摘をしている。
エンジンの内圧が上がり、ヘッドガスケットが抜ける症状があると言う。 最悪エンジン交換になるような、そうした話題についてEGRの仕組みも含めて解説している。
この動画の理解を深めるために、EGRについて、またEGRを強く効かせるディーゼル・エンジンの宿命についてまとめてみた。
EGRとは
EGR(Exhaust Gas Recirculation:排気再循環装置)は、自動車の内燃機関における排出ガス低減技術のひとつ。主に窒素酸化物(NOx)の削減を目的としている。 以下で仕組みと効果を整理しておこう。
1. EGRの基本原理
- エンジンの燃焼温度が高いほど、大気中の窒素(N₂)と酸素(O₂)が反応してNOxが大量に発生する。
- EGRは排気ガスの一部を再び吸気に戻すことで、吸気中の酸素濃度を薄め、燃焼温度を下げる。
- その結果、NOxの発生を大幅に抑制することができる。
2. EGRの種類
(1) 内部EGR(バルブタイミング制御型)
- 吸排気バルブの開閉タイミングを調整し、排気ガスを燃焼室に残す方式。
- 主に可変バルブタイミング(VVT)を使って制御する。
(2) 外部EGR(配管型)
- 排気マニホールドから吸気マニホールドに専用の配管とEGRバルブでガスを戻す方式。
- ガソリン車・ディーゼル車ともによく採用されている。
3. EGRの冷却
- 最近はEGRクーラーを使って、排気ガスを冷却してから吸気に戻す方式が一般的。
- 冷やすことで体積が減り、さらに燃焼温度の上昇を抑え、NOx低減効果が向上する。
- 特にディーゼルエンジンでは、EGRクーラーの効果が大きい。
4. メリットとデメリット
メリット
- NOx排出量の削減(環境規制への対応)。
- 一部の条件下ではポンピングロスを減らし、燃費改善にも寄与。
デメリット
- 排気ガス中の煤(スス)がEGRバルブや配管に堆積し、目詰まりや故障の原因になる。
- 吸気系が汚れやすく、長期的には性能低下を招く。
- メンテナンス(清掃や交換)が必要になることもある。
5. まとめ
EGRは「排気ガスを再利用して燃焼温度を下げ、NOxを減らす装置」。 環境規制が厳しい現代では、ガソリン車・ディーゼル車を問わず重要な技術だが、同時にメンテナンス性や堆積物対策が課題になっている。
排気のほぼ全量を一度「EGR経路」を通す設計の問題
最近のディーゼルや一部の高効率ガソリンエンジンでは、排気のほぼ全量を一度「EGR経路」を通す設計(クーラーEGRと高精度バルブを用いた「フルEGRループ」や「ロー・プレッシャーEGR」方式)が存在する。 これは環境規制に対応しつつ、燃焼を安定させる狙いがあるが、同時にいくつか大きなデメリットも伴う。
1. 吸気の汚染・堆積物の増加
- 排気ガスをほぼすべて吸気に戻すため、煤(スス)やオイルミストが大量に吸気系へ流入する。
- その結果:
- インテークマニホールドやEGRバルブが短期間で汚れる。
- 吸気ポートや吸気バルブ背面にカーボンが堆積し、吸気流量が制限される。
- スロットルレスポンスや燃費悪化の原因になる。
2. 出力性能の制約
- 吸気に酸素がほとんど含まれなくなるため、高負荷・高回転時に十分な燃焼ができない。
- そのため実際には、全負荷運転ではEGRバルブを閉じて「新気」を優先する必要があり、パワーと排ガス規制対応のトレードオフが発生する。
3. 燃焼安定性のリスク
- EGR比率が極端に高いと、燃焼速度が遅くなり失火やサージングが起きやすくなる。
- 特に低温時やアイドル時では燃焼が不安定になり、制御が難しくなる。
4. 熱負荷の増大
- 排気を大規模に戻すことで、EGRクーラーに強い熱負荷がかかる。
- EGRクーラーの冷却性能が不足すると、吸気温度が上昇 → 燃焼温度も上昇 → NOx削減効果が低下。
- クーラーの詰まりや故障リスクも増大。
5. システムの複雑化とコスト
- 大流量を扱うために、大容量のEGRクーラー・電子制御バルブ・センサー類が必要。
- 排気圧と吸気圧の差を常に監視しながら制御するため、ECUの制御ロジックが複雑化。
- 製造コスト・メンテナンスコストが上がる。
まとめ
「ほぼ全量EGR」の設計は、
- NOx削減には非常に有効で、規制対応を可能にする。
- ただし同時に、吸気系の汚れ・出力性能の制限・燃焼安定性の難しさ・システムコスト増というデメリットを伴う。
そのため、実際の市販車では運転領域ごとにEGR率をきめ細かく変える可変制御が使われており、「常時100%に近いEGR」は現実的には行われていない。
低回転・低負荷領域での「ほぼ全量EGR」特有の問題
低回転・低負荷領域での「ほぼ全量EGR」特有の問題については以下の通り:
1. 燃焼不安定・失火リスク
- 低回転では吸入空気量が少なく、シリンダー内のガス交換も不十分。
- そこに排気ガスをほぼ全量戻すと、酸素濃度が極端に低下 → 混合気が希薄になり過ぎて燃焼速度が遅くなる。
- 点火しても火炎伝播が不安定になり、失火・燃焼ムラが発生しやすい。
- 失火が増えると、かえってHC排出が増える。
2. エンジン応答性の悪化
- 低回転時は燃焼に必要なトルク余裕が少ないのに、EGRで酸素が不足しているため、ドライバーのアクセル操作に対してレスポンスが鈍くなる。
- 「もたつき感」や「加速のラグ」が強く出る。
3. 煤(スス)の発生と堆積
- 不完全燃焼になりやすく、低温での煤発生量が増加。
- この煤が吸気マニホールドやEGRバルブに堆積し、さらに流路を悪化させる負のスパイラル。
- ディーゼルでは特にDPFの再生頻度が増える。
4. 振動・騒音(NVH)の悪化
- 低回転で燃焼が不安定になると、燃焼圧力がサイクルごとにばらつき、振動やノッキング的な異音が発生しやすい。
- アイドルの「ハンチング(回転変動)」につながる。
5. 始動性・暖機性能の悪化
- コールドスタート時は特に燃焼安定が難しいのに、排気を大量に戻すとシリンダー温度が下がりすぎる。
- 暖機に時間がかかり、触媒やDPFの活性化も遅れる → 排ガスが増える。
まとめ
低回転時における「ほぼ全量EGR」の問題は、
- 燃焼不安定(失火・ムラ)
- レスポンス悪化(もたつき)
- 煤の増加と堆積
- 振動・騒音の増大
- 始動性・暖機性の悪化
といった形で現れる。
そのため実際のエンジン制御では、低回転・低負荷域ではEGR率を下げるか、あるいは一時的にEGRをカットして新気優先にする戦略をとっている。
経年劣化による内圧上昇の関係
「全量に近いEGR」を前提としたエンジン設計と、経年劣化による内圧上昇の関係について整理する。
これは動画で特に問題視している内容だ。
1. EGR設計とシリンダー内圧の関係
- EGRの大目的は燃焼温度を下げ、NOxを抑えること。
- 理論的には、排気ガスが多いほど燃焼は「緩やか」になり、最高圧力(ピーク燃焼圧)は低下傾向になる。
- したがって「新品・正常状態」では、EGRが多いほど内圧は下がる方向が基本。
2. 経年劣化で起こること
ところが、EGRシステムは経年で以下のトラブルを起こす。
- EGR通路やバルブの煤詰まり
→ EGR流量が減少し、想定より「新気」が多く入り、燃焼温度が上昇。
→ 結果的に燃焼圧が高くなる方向にシフト。 - EGRクーラーの目詰まり・劣化
→ 排気ガスが十分に冷却されず、高温のまま吸気へ戻る。
→ 燃焼温度抑制効果が弱まり、同じく内圧上昇のリスク。 - インテーク系の堆積物
→ 吸気ポートや吸気バルブが狭まり、流入空気の流動が乱れる。
→ 燃焼ムラや局所的な高温燃焼が起きやすくなり、サイクルごとの圧力変動幅が増大。
3. 内圧上昇がもたらす結果
- ピストンやコンロッド、シリンダーヘッドガスケットなどへの機械的負荷増大。
- ディーゼルでは特に、ノッキングやプレイグニッションに近い燃焼が発生しやすくなる。
- 長期的にはエンジンの寿命を縮める要因となりうる。
4. 結論
設計時点では「全量に近いEGR=内圧低下方向」が基本。
しかし 経年劣化でEGR流量が落ちると、結果的に内圧が上がることは十分あり得る。
特に煤やオイルミストが多いディーゼル車では、EGR詰まりによる「本来の制御からのズレ」が内圧上昇を招きやすい。
まとめると:
「全量EGR前提だから内圧が高くなる」というより、経年劣化でEGRが正常に機能しなくなり、結果的に内圧が高くなる可能性がある、という表現が正確。
おわりに
CX-60やCX-80は欧州向けでは尿素SCR仕様であり、DPF+EGRだけの日本国内向け仕様とは事情が異なる。
技術的に困難という理由ではなく、日本の市場性(メンテ性やコストアップ)を配慮して国内向けはEGR頼りの仕様にしたのだと推測される。
しかし、DPF+EGRのみの仕様にすることで、かえってユーザーのメンテナンス性が悪化しコストアップをしてしまっている。動画でも言われている通り、本末転倒である。