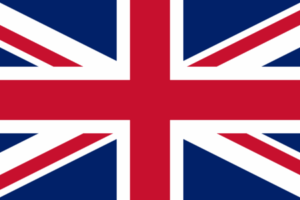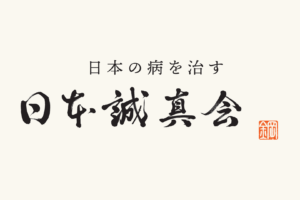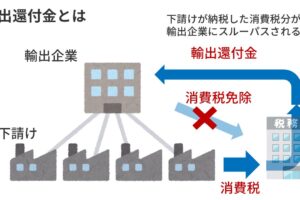先日、日本誠真会の党員・活動支援者向けに限定公開された動画「2025年参議院選挙における敗因分析と現状把握」を視聴した。
私はすでに党員をやめている立場だが、党本部からリンクが送られてきた。 「結果および振り返り」ということで関心を持って視聴した。 ここではその内容についての所感を述べたい。
目次
良かった点
良かった点は以下のポイントだと思う:
- 数字を用いて現状を具体的に把握し、そのうえで敗因を分析している
- 課題と今後の改善方針を出している
特に今回・過去の新興勢力の得票数と比較して、それぞれの実力を分析し、またネット政党の限界について言及している点は評価できる。 党員や支援者にとっては現実を直視する材料になったと思う。
また、敗因を分析したうえで課題を抽出し、改善のための方針を出したという点は姿勢として評価できるだろう。
物足りない点
一方で、いくつか物足りなさや課題を感じた。
勝算と結果とのギャップへの言及不足
出馬にあたっては「これくらいは得票できるだろう」という見込みがあったはずだ。 しかし、動画では事前の勝算と結果へのギャップへの言及がなかった。
どれくらいの得票を目標としていて、そこに届かなかった原因を検証することも必要ではないか。
現状認識の甘さ
今回の日本誠真会は知名度は低く、各支部の組織が未整備のまま選挙戦に突入した。
その一方で「吉野敏明だけが当選すれば良いのであれば、大阪で立候補すれば当選できる」とまで発言していた。 しかし、本人の比例区での得票は30万票あまりであり、当確ライン100万票の3分の1だった。
こうした準備不足や戦略の欠如の自覚がなければ、また同じ轍を踏む可能性はあるだろう。
コラボ路線の限界
動画では知名度不足の理由として「TV露出の少なさ」を理由に挙げていたが、3年前の参政党はほぼ同様の条件下で議席を獲得した。 吉野敏明が武田邦彦の影響力を指摘していたが、その説明だけで十分だろうか?
知名度向上に関する今後の方針として「コラボの強化」の話があった。 過去にも、梅宮アンナ、長井秀和、平井宏治、三橋貴明、前田日明らがチャンネルに出演してきた。 しかし継続的な協力関係になっているとは言えないだろう。
なぜ継続的なコラボが実現しないのか、原因分析が必要だと感じる。 戦略的な理由があるのか、それとも党首自身のスタイルや姿勢に要因があるのか、を振り返る必要があるのではないか。
政策の独自性が分かりづらい
改善方針のなかで「難解な憲法論」をトーンダウンさせるという(「翻訳する」と言っている)。 だが日本誠真会が参政党との違いとして強調してきたのは、まだにこの「憲法論」だ。
こうなると参政党との差はさらに分かりづらくなる。 参政党にアレルギーがない人は、自然と参政党に投票するだろう。 となると、日本誠真会を支持するのはアンチ参政党の保守層か、吉野敏明の個人的ファンに限定される。
選挙区擁立が8人にとどまった理由の説明がない
吉野敏明は「45の選挙区全部で候補者を擁立するから2億円以上必要」と何度も寄付を呼び掛けてきたし、相当な額の寄付金を集めた。 しかし実際には8人にとどまった。今回の動画でも、この件について明確な説明はなかった。
また各選挙区では、立候補の誘いがありながら実現しなかった人、立候補が内定しながら取り止めた、などの例を聞いている。
こうした不透明な党運営について説明責任を果たしていないと感じる動画であった。 「誠意と真実と敬い」を掲げる党であるなら、その通り実行するべきだろう。
総括
敗因分析や改善方針を説明したこと自体は評価できる。一方で、真因の追求にはまったく物足りない内容であった。 保守系政党を応援したい気持ちはあるのだが、日本誠真会には何か根本的なものが足りないように思えてならない。
残念ながら、この動画を見ても日本誠真会を応援したい気持ちが私のなかで再び湧き上がることはなかった。