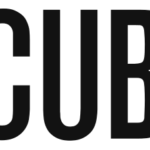(更新日: 2022年4月12日 )
昨年の12月に山形県鶴岡市に出張して、地方の雰囲気をあらためて感じてきました。 そんなふん詰まった生々しさを感じてから読むと、この本に描かれている町の雰囲気がより分かるかも。
都会ではないところの出身者ならではの屈折と諦めとも言える日常とでも形容するべきか、「分かるわー」となるか「分からん」となるか。 これを読んで自分の出身地である浜松にいる高校の同級生達の憧れ半分妬み半分のような(だけではないと思うけど)複雑な思いは、少し分かったような気になりました。 「地元」に戻るという選択肢は、ぼくには無かったなーとぼんやり考えながら、それでもどこかヒリヒリするような思いで読み進めました。
同時に、修善寺出身の大学の同期が東京に強い憧れを持っていて、東京での生活を心底堪能していたのを当時はさっぱり心情が理解できなかったのを思い出しました。 そういう意味だと、地方に戻ったほうに、ぼくは近いのかも。
中身は何人かの主人公のオムニバス形式の短編集。 基本は女性が主人公で、なぜか椎名くんという一人の男性だけが共通して現れるという設定は少し面白い。 いつまでも忘れられない良い感じの異性がいる、というのはありそうだし、地方だとその存在が割と大きいというのはもっとありそう。 そして、30歳過ぎて再会して昔ほどの輝きはない、なんていうのもありそう。実際には無いのかも知れない。
都会から戻る者、都会に向かう者、まんまの人はいないと思うけど似た感じはいそうだと思えるストーリーで、どれもどこか痛みを感じながら読んで止まりません。 なかでも「私たちがすごかった栄光の話」のエンディングが好きです。