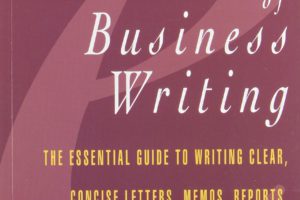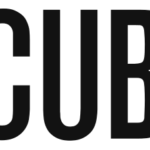(更新日: 2017年9月19日 )

2016年は夏目漱石の没後100年でした。というのはこの本を読んでから知りました。この十川信介による夏目漱石は、その没後100年になんとか間に合わせたようです。
この本は、夏目漱石の生涯と作品の解説です。 本書の最後に漱石の年表がまとめてあります。夏目漱石の作家としての活動期間11年ほど、というのが驚きです。その間の中長編小説が15編。 1911年以外は毎年作品を発表しています(1910年は死にかけています。有名な修善寺の大患ですね。)
作家になる前の解説もとても充実しています。漱石の理解には、欠かせない部分でしょう。 複雑な生い立ちの部分も詳しいですね。アダルト・チルドレン的な出生は読み取れますが、あまりそういう読み方はしていない(まあ当然でしょう)。 イギリス留学の背景、イギリスでの生活についても詳しく書いてあります。かなりよく調べていると思いました。
病気の記述も多い。胃潰瘍、痔。痔は手術で治したようですが、胃は最後まで悩まされたようです。
作品の解説としては、虞美人草の部分が興味深い。「自然を描写するときは形容に意を用いすぎるのが、この時代の彼の癖であった」とか「物語的な完結を急ぎすぎた感も否めない」とか、漱石も時代によって特徴があるのかと改めて思わされました。このような分析はもっと読みたいと思わせます。
順番は前後しますが、(最近読み直したばかりの)坊っちゃんの解説もとても面白い。清が本当の母親説は信憑性が高いですね。坊っちゃんを読んでいる時はもやもやしていましたが、そういうことかと納得が行きます。漱石の特徴として、全部を説明しない作風があるように思えます。それくらいは汲み取れということかも知れません。読者に任せるせいで深みが増すというか、奥行きがでるということでしょうかね。
「三四郎」「それから」「門」は、私が高校生のころは三部作として読みましたが、本書ではそのような扱いはしていないようですね。「それから」と「門」は関連があるように書かれています。三四郎については、本書の人間関係のまとめが分かりやすく、また読んでみたいと思います。
漱石の後期の作品群である「彼岸過迄」「行人」「こころ」「道草」「明暗」については、私は「こころ」を除いてあまり内容を覚えていません。この本を読みながら、読んでいこうかなと思います。
漱石の論説文としては、全体的に江藤淳のものと比べてドライというか冷静な記述の印象を受けます。逆に、そのために漱石の姿が感動的に思えます。この著者の文体も、格調があって味わいがあると思います。 (江藤淳の場合は、思いが強いというか思い込みが激しいというか、漱石のことよりも江藤淳の思いが主になっている気がしますね。それはそれで面白いし、そういう評論もあって良いと思う)。