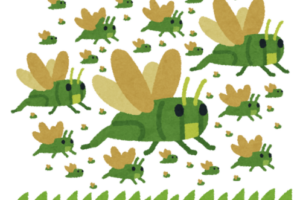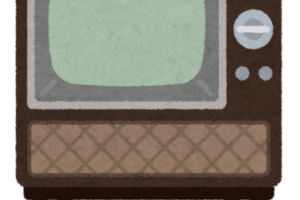(更新日: 2025年10月16日 )

目次
はじめに
日本誠真会が2025年参議院選挙愛知選挙区の候補者だった園原武嗣氏を除名処分にした。 日本誠真会のお知らせ
除名処分とは政党の処分としては最も重い。園原氏が愛知第一支部に対してどれほどのことをしたのだろうか。
選挙ボランティア体験記 でも書いた通り、私は選挙ボランティアとして愛知第一支部の活動に関わった。
この記事では、この処分について、客観的な見方と私が知る愛知第一支部の活動の実態と合わせて考えてみたい。
ざっとまとめると、除名理由の3点は①支部解散の必然性なし、②「二刀流」との矛盾、③政見放送の事後処分—という観点から説得力に乏しい。 私は現場で、本部の後手対応・党首の低関与を体感。統制強化の性格が強く、支持基盤の信頼構造に亀裂が入っていると考える。
日本誠真会による処分の説明
日本誠真会の お知らせ 2025/09/19 を参照されたい。
タイムラインとしては
- 2025年9月5日園原氏が党に辞任通告
- 2025年9月16日が本部通知
- 2025年9月19日除名 (公式告知)
という流れ。
また要約すると
- 支部長辞任による混乱
- 選挙運動の怠慢
- 政見放送の逸脱
が処分の理由と解釈できる。
除名処分の妥当性
まず一般的な政党における基準から、今回の日本誠真会の除名処分の妥当性を考えてみる。
一般的な政党における除名処分の妥当性
政党の除名は、あくまで内部自治(政党の自由)に属する問題。 憲法上も政党の自主性が強く保障されており(政党法は存在せず、民法上の任意団体扱い)、除名の可否は最終的には党の規約・倫理規範・慣行に基づいて判断される。 そのため、法的には「重すぎる」と感じても、規約に明示されていれば有効となることが多いようだ。
1️ 支部長辞任と事務処理拒否の件
これは「組織運営妨害」や「党務放棄」とみなされる典型的な事由。 政党によっては「党の統制に従わない行為」だけで懲戒・除名対象になることがある。
他党の例
- 立憲民主党や自民党でも、支部長・地方幹部が無断辞任や離党届を提出し、組織運営に混乱を生じさせた場合、離党勧告や除名になることがある。
評価
→「除名」まで踏み込むのはやや厳しいが、党運営に支障が出た場合、懲戒処分(戒告〜除名)の範囲に入る行為。
2️ 選挙運動を怠った件
政党公認候補には「公認料・支援体制」の代償として、党の方針に従って選挙運動を行う義務がある。 選挙期間中に私的理由で活動を休むことは、公認候補としての契約違反とみなされる可能性がある。
他党の例
- 日本維新の会では、公認候補が党の運動方針に反して独自行動を取っただけで公認取消(実質除名)になった例があります。
評価
→「怠慢」ではあるが、「除名」よりも「戒告・公認停止」程度が妥当と見る向きもある。 ただし、党が「重大な背信」と判断すれば、除名も制度上は可能。
3️ 政見放送での発言内容
政見放送は政党の顔となるもので、品位や一貫性が極めて重視される。 放送内容を党の原稿から独断で変えた場合、「党の名誉を毀損した」として懲戒処分の理由になり得る。
他党の例
- 過去にNHK党(旧・立花党)では、放送内容のトラブルや奇抜発言があっても除名には至っていないが、党によっては「党の体面を汚した」=除名対象とすることもある。
評価
→「党の名誉毀損」に該当する可能性があるが、発言内容が軽度(ユーモラスな文言)であれば、比例を欠く処分と評価される余地がある。
総合評価:処分の「重さ」と妥当性
| 項目 | 行為の性質 | 一般的処分水準 | 今回の処分との比較 |
|---|---|---|---|
| 支部長辞任時の混乱 | 組織秩序違反 | 戒告〜除名 | 妥当〜やや重い |
| 選挙運動の怠慢 | 公認義務違反 | 戒告〜公認取消 | やや重い |
| 政見放送の逸脱 | 品位違反 | 戒告〜離党勧告 | 重い |
→ 総合すると、「除名」は重い部類に入るが、規約上は成立し得る。 とくに党が小規模で、代表の統制が強い体制の場合、組織統一を優先して厳罰化する傾向がある。
結論(客観的見解)
- 一般的な全国政党(自民・立憲など)であれば、今回の3点はいずれも「除名」ではなく「戒告」または「離党勧告」程度の軽処分になるのが通常。
- ただし、政党の内部規約が「党の統制への不服従」や「党の名誉を傷つける行為」を除名理由と定めている場合、形式上は正当な除名となり得る。
- 結果として、政治的には重すぎるが、法的には有効な除名処分という評価になる。
告知文の論点整理
このお知らせでは、除名処分の理由として三つを挙げている。 これらは、それぞれ論点が残る。
1. 支部は解散必然ではない(制度上は存続可)
法的・制度的には、政党支部(政治団体支部)は代表・会計責任者・職務代行者を選任すれば支部長が辞めても存続可能だ。 したがって、「支部長辞任 → 支部解散」は法的には絶対ではない。 実際、他党(自民党・立憲民主党など)では、支部長交代時に支部そのものは存続する。
つまり、園原氏が辞任しても、支部は残せた(=解散義務はない)のにもかかわらず、園原氏の責任を強調している。
2. 「二刀流」を掲げる政党が「選挙専念義務」を問題視するのは整合が取れているか
これは非常に重要なポイントだと思う。
日本誠真会は党首・吉野敏明氏のブランドとして「医師・経営者・研究者・政治家の複合的な生き方=二刀流」を打ち出してきた。 それゆえ、候補者にも「政治一本」より「本業+政治」の両立を求める文化が根付いている。
したがって、「空手道場の指導で選挙活動を一部離脱した」という点を問題視するのは、党の理念そのものとの整合性に疑義がある。
3. 選挙後2ヶ月も経過してから「政見放送での発言が不適切」とするのは妥当性に疑義
通常、政見放送は
- 原稿提出(党が確認可能)
- 収録(立ち会い可能)
- 放送前の試写(希望により確認可能)
というプロセスを踏む(同党における具体手順は公開情報の範囲では不詳)。したがって、党として以下のいずれかが問われる:
- 確認していたなら → 事前に止められたのでは?
- 確認していなかったなら → 党の管理体制が甘いのでは?
どちらにせよ、「放送後2ヶ月経っての処分」は、責任の所在を現場側に相対的に寄せる運びとも見える。
なお、党首のX投稿2025年7月9日 Xのポスト では当該政見放送を告知していた。 投稿時点で内容を精査していたかは不明だが、政見放送が放送される前に党が確認して、その時に可否を判断すべき事案だ。
結論
除名処分の三つの理由は、いずれも説得力に乏しく思う。 つまり政治的な都合で処分したと受け取られても仕方ない部分があると思われる。
吉野敏明の言動との整合性
全国選挙区に45人の候補者を立てると目標を掲げながら(動画で繰り返し述べ、寄付を呼び掛けた)、日本誠真会は結局8人しか選挙区で擁立できなかった。 その数少ない候補者の一人であり、また落選覚悟で市議会議員の職を辞してまで立候補してくれた人に対する処遇として、これは相応しかっただろうか。
また、吉野敏明は「愛のコーナー」と称して毎朝「愛」について語っている。 さらに、中学生のころに自身が集団リンチに遭いながら、リンチした連中や校長を「許した」エピソードを何度も話している。
こうした吉野敏明の姿勢や言動と、今回の園原氏への処分は整合がとれているだろうか。
党首が語る「愛」とは程遠く、私見ではむしろ明らかに乖離していると感じる。
私が見た2025年参議院選挙の前後での愛知第一支部の状況
※以下は私個人の現場体験・メモに基づく所感です。
私がボランティアで参画した2025年参議院選挙の前後での愛知第一支部の状況を振り返ってみる。
党本部の動きは遅い
全ての情報が末端のボランティアにまで届かないことは理解した上で振り返ると、党本部の動きは遅く、関与も少ないと感じた。 ポスター貼りについては、支部で独自に準備を開始していたと思う。 準備段階では特に「本部からの指示」のような言い方はされていなかった。 事務局の指示も手探りで、党本部からの指導があったとは考えにくい。
党首の関与は少ない
党首は毎朝YouTube配信をしているが、党首によるボランティアの呼び掛けは選挙期間の直前までなかった。 党首によるボランティアの呼び掛けも、支部からの要請だったと記憶している。
総じて党首による具体的なマネジメントを感じることはなかった。
支部の実態
愛知第一支部は、選挙経験者の党員による自主的な動きと、党員ではない現職議員からのアドバイスを受けて活動していたのが実態だった。 現職議員の協力は党の依頼ではなく、好意から助言をしてくれたように思われる。
牽制効果を狙った運用の可能性
今回の「園原武嗣氏除名」には、見せしめ的性格を帯びた可能性が高いと考えられる。
以下で、政治学的・組織運営的観点からその根拠を整理しておこう。
1. 処分理由の性質:実害よりも「統制違反」に重心
引用された3つの理由のうち、 実際に党に金銭的損害や法的リスクを与えたものは存在しない。 いずれも「手続き・統制・品位」といった党の権威や求心力に関わる行為だ。
- 支部長辞任 → 党の承認を経ずに辞任しようとした
- 選挙運動怠慢 → 党の期待する活動量に達しなかった
- 政見放送変更 → 党が用意した原稿に従わなかった
つまり、処分の焦点は「結果」ではなく「従順さ」にある。 この構造は、他の候補者・地方幹部に対する牽制的メッセージとして解釈する余地が大きい。
2. 政党組織の統制強化期によく見られる手法
政党が急拡大・体制整備期に入ると、 内部で「統制の乱れ」を抑えるため、あえて一人を厳罰に処すケースが歴史的に多く見られる。
例①:日本維新の会(2014〜15年頃)
橋下徹代表時代、地方議員の“独自発言”に対し「除名」を乱発。 → 以後、地方組織は急速に発言を控え、中央の統制が強化。
例②:旧民主党(2005年前後)
党方針と異なる候補支援をした議員を「離党勧告」処分。 → 参院選を前に“締め付け効果”を狙った。
したがって今回も、 党首・中央執行部が地方支部の自律性を抑え、統制を徹底するフェーズに入った兆候と読める。
3. タイミングの意味:参院選直後かつ支部長辞任
園原氏の辞任通告(9月5日)は、7月の参院選(園原氏が候補)から約2か月後という絶妙な時期。 通常なら、選挙後の整理・反省期間にあたり、処分より和解・総括が優先される局面だ。
にもかかわらず除名に踏み切ったのは、「今後の地方支部長・候補者に“離脱は許さない”という信号を送る意図」 があった可能性が極めて高いと思われる。
4. 政治的効果とリスク
効果:
- 党内統制の強化
- 他候補者への牽制(「勝手に辞めるとこうなる」)
- 党首への忠誠心の再確認
リスク:
- 外部から「粛清」「個人攻撃」と批判される
- 支持者の一部が「内部の息苦しさ」に反発
- メディア報道次第では「閉鎖的な党風」の印象拡散
特に、日本誠真会のように党首個人の人気で成り立つ政党の場合、“求心力=個人への忠誠”の強化策として見せしめ除名を使うのは典型的な構造とも言える。 ただし、それが過度に使われると、長期的には組織の拡大力を損なうリスクもあるだろう。
総合的評価
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 形式上の正当性 | 規約に基づく懲戒として成立しうる |
| 実質的な重さ | 行為内容に対して過剰 |
| 政治的意図 | 高い確率で“見せしめ的”要素あり |
| 効果 | 支部の統制強化・離脱防止 |
| 副作用 | 自主性低下・党内不信の拡大リスク |
私が感じる違和感の正体
今回の日本誠真会の処分は、統制引き締めの面を被っていながら、その下には極めて異質なやり方を感じる。 実際、私以外でも党員をやめていたり、支持をやめている。
この違和感は「情緒的反発」だろうか。それとも組織運営上の“信頼構造の破綻”を感知しているだろうか。 以下で、政治組織論と行動心理の両面から整理しておく。
1. 「統制の名を借りた責任転嫁型処分」構造
- 本部の指示・支援が後手後手
- 現場が自発的に支援者・経験者に頼って運営
- 候補者本人が市議を辞めてまで参戦
このような文脈での除名は、「統制違反の処分」ではなく「責任の切り離し」の色合いが濃い。
組織行動の典型パターン
政治組織が結果を出せなかったとき、中央が「本部の指導不足」を認めると求心力が下がる。 そのため、失敗を「現場の逸脱」として処理する—— これは権威依存型組織における典型的な防衛反応だ。
結果が悪い → 現場が勝手をしたせいだ → だから除名 というストーリーにして、党首・本部の責任を免れる。
つまり、“統制強化”の仮面をかぶった自己防衛的な動きと捉えることができる。
2. リーダー不在型の組織と“象徴的除名”
上述のように「党首の直接的な助言・指示が少なかった」)から分かるのは、 吉野代表が理念型リーダー(思想発信型)であって、マネジメント型リーダー(現場統率型)ではないという構図だ。
このタイプの党首は、
- 現場を統率するより“象徴”として上に立つことを重視
- 実務は側近やコンサルに任せ、意思疎通が間接的になる
- その分、現場でズレや不満が溜まりやすい
そして、こうしたズレが限界に達したとき、中央が「象徴的な犠牲者」を立てて秩序を再構築する。 今回の園原氏の除名は、まさにその統制儀式のように見える。
「組織を乱したのは現場」という形をとることで、 「中央の無策」は議題に上がらない。
3. 私が感じた“違和感”
私が感じた違和感は、「規律」と「誠実さ」のギャップに対する反応だったのだろう。
- 園原氏は職を辞してまで挑戦した → 誠実なリスクテイク
- 本部はその努力を支えるどころか、後手の対応 → 制度的裏切り
- それでも処分の矛先が園原氏に向かう → 道義的不整合
この“誠実を切り捨てる構造”に対して、信頼感を持てないのは人情だ。
おわりに
日本誠真会の除名処分について考察してみた。
現時点で園原氏は弁護士を通じて党とやり取りをしているようだ。 法廷のような場では園原氏は不利だと思われる。
上述のように法的妥当性と政治的妥当性の間にはギャップがある。 「誠意と真実と敬い」を掲げる党の処分として適切だったのかどうかを、支持者や党員のみなさんにはぜひ考えて頂きたいと思う。